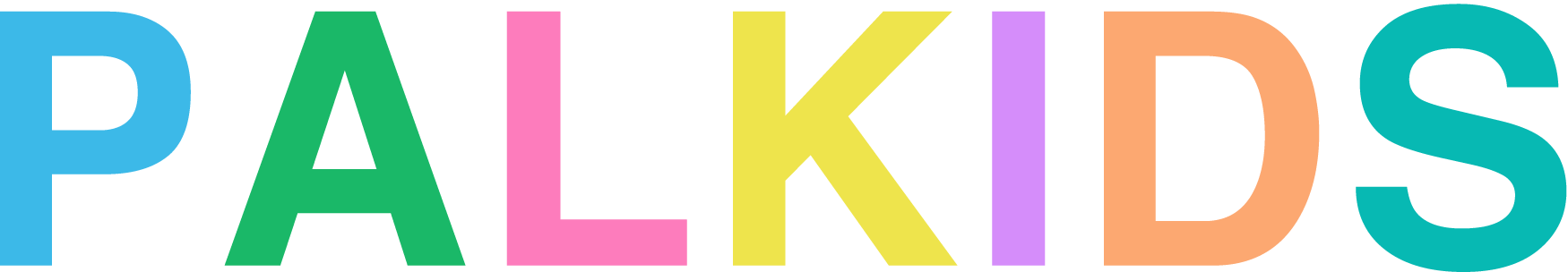パルキッズ通信 特集 | 発音, 英語環境, 言語獲得装置, 言語発達, 読解力育成

2015年08月号特集
Vol.209 | 「成果が見えない…」と思ったママへ
言語学的に見たお子さまの成長段階をやさしく解説
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
http://palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-1508/
船津洋『「成果が見えない…」と思ったママへ』(株式会社 児童英語研究所、2015年)
子どもたちは言語獲得の過程において、様々な表情を見せます。
成長している様子が分かれば、親は喜びます。しかし、成長を見せずに親を心配させる時期もあります。「均衡期」と呼ばれるこの時期には、子どもたちは新たに獲得した言語能力をフルに楽しんでいます。そして、フルに楽しみながらも次の段階へ向けての学習を、密かに進めています。これは目には見えません。ですから、一見すると学習していない、まるで成長していないかのように見えてしまいます。
やがて、子どもたちは、この均衡期における日々の言語活動を繰り返しながら、「何かがおかしい」と感じ始めます。どうやら自分が行っている言語活動、たとえば、1歳半ならば単語単位のコミュニケーション、2歳代なら単純な二語文の会話が、未熟であるらしいことに気付き始めるのです。そのようにして、均衡期にはいろいろな発見が行われます。そしてそれらが、言語発達の次の段階へのエネルギーとなるのです。
そして、十分な言語刺激が蓄積されてエネルギーが爆発すると、次のステージへと進めます。この時期はとても不均衡な時期です。たとえば、歩き始めた子がよちよち歩きをするように、危なっかしい時期なのですが、親の目から見れば、この「不均衡期」が成長と映るのです。
このように、均衡期と不均衡期を繰り返しながら学習は進みます。
これは、幼児の言語習得に限ったことではありません。どんな技術の習得もこのようなステージを経て進行します。日々淡々と繰り返し勉強をしているうちに、ある日突然ぱっと視界が開ける感覚、何度も練習して初めて1人で自転車に乗れた時の感覚、初めてスキーが出来た、スノーボードが出来た…。何かが初めて出来たときの、あの感じです。しかし、こういった急激な成長と見える「不均衡期」に至るまでには、準備段階とも呼べる「均衡期」があるのです。
残念なことに多くの親御さんが、この均衡期を目にすると、「学習が進んでいない」と思い込んでしまい、学習を中断させてしまいます。均衡期こそが、学習が進んでいる時期にもかかわらず、もったいないこと極まりない話です。
また、子どもたちは、発達段階で何も変化を見せないのならまだしも、退化とも映る現象を見せることすらあります。たとえば、英語の発達を例に取ると、1歳前後では ‘pretty’ を大人と同じように [priti] と発音できるのですが、2歳に近づくにつれて [piti] となり、仕舞いには [bidi] となることすらあるのです。
これは、’phonological process’ と呼ばれる言語の簡略化です。単に周囲の発音をまねしている段階から、二語文を話すようになる時期に、このようなことが起こります。言語には(「最小限の労力で最大限のコミュニケーションを行う」という)「経済理論」が働きます。言ってしまえば、「手抜き」です。あるひとつのこと(二語文)をマスターするのに忙しく、ほかの作業(発音)が雑になり、より楽な方へと引っ張られるのです。もちろん、これが延々と続くのではありません。二語文の獲得が完了すれば、また元通りに [priti] と発音できるようになるのです。このようにひとたび出来たことが、次の成長段階では出来なくなることを ‘U-shaped Development’ (U型発達)と呼びます。一旦下って、また上がるのをUの字になぞらえた呼称です。
この現象は、発音にのみ見られるのではなく、文法面でも見られます。たとえば2歳では “doggie ran” と正しく過去形を使えていたのに、3歳にかけての文法学習が進む時期には “doggie runned” と文法的に間違えた発話をするのです。この時期、彼らは他の動詞の多くが ‘-ed’ をつけることで過去形になるという原理に気づきます。そして、その文法ルールを不規則変化の動詞にも当てはめて ‘runned’ とするのです。しかし、これもまたずっと続くわけではなく、不規則動詞があることが理解できれば、きちんと文法に沿った発話をするようになります。
また、身近なところでは、絵本の暗唱が進むに連れてこのような変化が見られます。単純に音をまねしているだけの時点では、子どもたちの発音は、音源にあるネイティブの発音のようにきれいです。子どもたちは「まね」をすることが非常に上手なのです。ところが、絵本の暗唱を続けるうちに、発音が退化を見せることがあります。
絵本の暗唱の目的は、「読解力の育成」にあります。仕組みとしてはとても単純な取り組みで、丸暗記した音を口にしながら絵本をめくる、そのうちに自分が口にしている音声と、絵本に印刷されている文字との関係に気付き始めます。「ああ、これを口にしているのか!」と気づくのです。すると、今度は文字が気になって仕方がありません。そして、そちらに気を取られていると、発音が悪くなってしまうのです。
この状態がある程度続くと、学習が進み、文字を読めるようになります。するとまた、元のきれいな発音に戻るのです。
このように、言語学習の側面は、様々に観察されています。それらはあくまでも観察やそれに基づく仮説の状態で、まだまだ未知の世界です。
従来、言語は表出されたものを研究の対象としていました。頭の中で考えていることも含め、発話や記述を通して「脳内から外の世界へ送り出された言葉」を研究の対象としてきました。その中から、日本語の文法や英語の文法といった、規則性の発見が行われてきたのです。
ところが、20世紀の半ば頃から少し様子が変わってきました。古典的な言語の研究は、たとえば「日本語はどんな特性を持った言語なのか、英語とはどのような違いを持っているのか」といった点に研究の重点が置かれていました。それが、現在では「日本語はなぜこのような特徴を表すのか、英語はなぜこのような特質を持っているのか」というように、命題の質が「どのような」から「なぜ」へと変わっているのです。
この考え方の根本となっているのが、チョムスキーによって提唱された「普遍文法」の考え方です。
従来の考え方では、人の言語獲得は、様々な言語体験を通して得られた情報の帰納によると考えられていました。ところが、幼児たちは言語環境には存在し得ない言語を発話するのです。先に述べた言い間違えなど、経験したことのない新しい言葉を、彼らは生成します。この点の説明が付きにくかったのです。また、疑問はそれだけではありません。幼児たちがわずか2、3年の間に、どのようにして複雑な言語体系を獲得できるのか、この点も大昔から延々と議論が続いてきました。しかし、「経験的に」とか「現環境があるから」といった、フワッとした答えしか見付けられなかったのです。
ところが、チョムスキーの「普遍文法」に当てはめると、ありとあらゆる言語活動に答えが見つかるという、なかなか画期的な考え方なのです。
世界には、5,000とも7,000とも言われる言語が存在しますが、それらの言語は人間が生まれつき持っている「普遍文法」から生成されるというのが、その考え方です。普遍文法は、少数の基本原理「プリンシパル」と、スイッチのオン/オフのような「パラメーター」からなります。
プリンシパルの一例に ‘head at edge’ があります。’head’ とは句の主要部のことで、たとえば動詞句においての動詞の位置を見ると、それらの主要部は必ず句構造の端に現れる ‘head at edge’ という点です。
たとえば「私は学校へ行く」という文章をみると、「私は」と「学校へ行く」の2つに分解できますが、動詞句である「学校へ行く」の主要部「行く」、さらに分解すれば動詞句「行く」の中で現在形を表す「く」はいずれも句構造の端に現れています。これがヒトの言語の基本原理のひとつです。
一方、パラメーターはたくさんあります。同じく、句の主要部の位置に着目すると、日本語の場合には ‘head final’ と設定されていて、つまり句の主要部は句構造の一番最後に来ます。名詞句「私は」の主要部は、この句が続く文章の主題を決めることを決定する「は」であり、同様に「学校へ」では後置詞句(日本語の助詞は言語学では英語に見られる前置詞との対比からこのように呼ばれる)の性質を決定する「へ」、さらに「行く」においては動詞の性質を決定する「く」が、いずれも句構造の最後に現れるようにパラメーターが設定されています。
この点、英語は真逆の振る舞いを見せます。 “John goes to school.” では名詞句の主要部の ‘John’(これは1語で成立している句ですが)、また動詞句 ‘goes to school’ では句の意味を決定する ‘goes’ が、さらに前置詞句 ‘to school’ ではその性質を決定付ける ‘to’ が、いずれも句構造の最初に現れる ‘head initial’ と設定されているのです。
ほかにも、s を付けたりする複数や性別の有無、wh疑問の際の疑問詞の文頭移動、疑問助詞の有無などのパラメーターがあります。ちなみに、日本語の場合には疑問助詞「か」があり、この「か」を文末につけることによって(「行きますか」など)疑問文が生成されます。また、wh疑問の「だれが」とか「なにが」は肯定文の時と同じ位置にあり(「あなたはどこに行きますか」など)、英語のように文頭に移動する(”Where does John go?”など)必要がありません。このようなパラメーターを様々な組み合わせで設定することにより、世界中に数千ある言語の多様性が生まれるのです。
一方で、言語には普遍性があります。その一端は、幼児の言語獲得に見て取ることが出来ます。幼児の言語獲得においては、ヒトの言語に共通する普遍性があります。
まず、極めて短期間に学習が行われる点です。子どもは生まれるとまず cooing や babbling (喃語)と呼ばれる発声を始めます。この段階では彼らは言語として音声を使っているのではなく、音自体で遊んでいる段階です。何からのコミュニケートを図っているケースもあるでしょう。
余談ですが、言語はコミュニケーションの手段と言われますが、ヒトのコミュニケーションの中で「言語」が占める割合は7%とか30%などと言われます。言語はコミュニケーションの重要な要素ですが、コミュニケーションのために言語があるのではありません。言語がなければ、つまり語彙も概念もないということになり、思考自体が成立しません。言語は思考のためにある、と考えた方が自然かもしれません。また、コミュニケーションという点ではミツバチやサル、イルカなどもお互いに何らかのコミュニケーションをします。しかし、音声は使うものの、ヒトの言語のように無限の表現を生み出せるわけではありません。この点、言語の保持はヒトを他の生物から決定的に独立させているのです。
さて、話を幼児の言語獲得へ戻しましょう。幼児たちは暫くすると「喃語」を話し始めます。明らかに何事かを伝えようとしているのですが、この段階ではまだ何を言っているのか分かりません。そして、1歳前後になるとようやく意味のある言葉を話し始めます。そして、2歳で二語文、3歳で言語の基本部分の獲得は終了します。
次に、幼児たちは能力の差に関係なく、誰でも言語を身につけられます。大人になってからの言語習得を想像すれば明白ですが、言語とは難解極まりない代物で、相当優秀な人でなければ、大人になってからネイティブレベルの外国語を身につけるのは難しいでしょう。ところが、幼児期であれば、難関大学へ行くような頭脳や努力がなくとも、言語を身につけることが出来るのです。そして、これは日本語に限らず、すべての言語に共通しています。幼児はわずか3年ほどで、等しく母語を身につけていくのです。
さらに、環境について考えると、少なからず衝撃的です。幼児が言語を身につけていく過程に存在する言語環境は、質量ともに必ずしも優れた情報ではないのです。語彙的にも乏しく、文法的にも文章としても不完全な状態で与えられることが多いのです。
さらに、興味深い点は、誰一人として同じ言語環境で育っていないにもかかわらず、得られる言語能力にはほとんど差はなく、均一の質であるという点です。家庭によっては、知的会話が中心に行われる環境もあるでしょうし、そうでない環境もあります。また、もの静かな母親のもとに育つ子と、にぎやかな母親のもとに育つ子では、与えられる言語の量は比べものにならないはずです。それにもかかわらず、ヒトの言語力には大差がありません。もちろん、語彙力や運用能力においての個体差は激しいのですが、一般的な事柄を理解したり、卑近な話をする場合の言語運用において、個体差はほぼないのです。
さらに、否定証拠が与えられない点においても、幼児の言語獲得は共通しています。子どもたちが文法的に間違えたことを言っても、親は否定しません。親が言語学者でもない限り、子どもたちの言葉の誤用には通常意識が向かないのです。
親は、子どもの発話の文法的正確さではなく、その内容を聞いています。そして、子どもが事実と異なったことを言ったときに反応するのです。たとえば、1歳半の我が子が見知らぬ男性を指さして「パパいた」と言えば、「パパじゃないでしょう」と訂正するような反応です。「できられない」などの文法ミスに関しても、発語の否定や文法の訂正をする親は皆無でしょう。このように、否定証拠は与えられないにもかかわらず、いつしか正しい文法知識を身につけていくのです。
以上のように、(1)子どもたちは短期間で、(2)能力の差に関係なく、(3)不完全な文章ばかり与えられる環境にいても、(4)どの子も均一の日本語文法を身につけます。しかも、(5)周囲の大人たちに日本語自体を教えられることなく、です。
これらは、普遍文法のパリンシプルとパラメーターの考え方で説明が付けられます。
短期間で身につけられるのは、大量の言語情報から文法を帰納するのではなく、「複数形:あり/なし」「疑問詞:あり/なし」とスイッチを入れていくだけで良いから可能となるのです。また、パラメーターのスイッチを入れるだけなら、個体の能力に依存することが少ないので、誰でも等しく身につけることが出来ます。同様にパラメーターのスイッチのオン/オフを判断する材料としては、それほど優れた言語情報は必要ではないともいえます。さらに、各パラメーターの値は、日本語の母語話者に共通しています。ある人は複数形がオンで、別の人はオフになっている、などということはあり得ません。つまり、同質の日本語文法を身につけていくのです。
「言語はヒトに生来備わっている能力なので、学習したり獲得したりするものですらなく、育つものだ」とする考え方まであります。それほど、言語は時期と方法さえ間違えなければ、簡単に身につけることのできる代物なのです。
幼児期の英語獲得に関しては、まだまだ学問が進んでおらず、諸子百家の様相を呈していますが、上記のようにすでに分かっていることもあります。また、現に子どもたちが日本語を身につけている点、またパルキッズなどを使って英語を身につけている点などを、バイアスなく冷静な思考を持って受け止めれば、常識的に理解できる点もたくさんあります。
ただ、環境がなければスイッチも入らないのですから、この環境作りだけはしっかりと続けてください。特に夏休みは生活のリズムが乱れがちです。英語の環境作りのリズムまで崩れないように心がけましょう。

船津 洋(Funatsu Hiroshi)
株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。