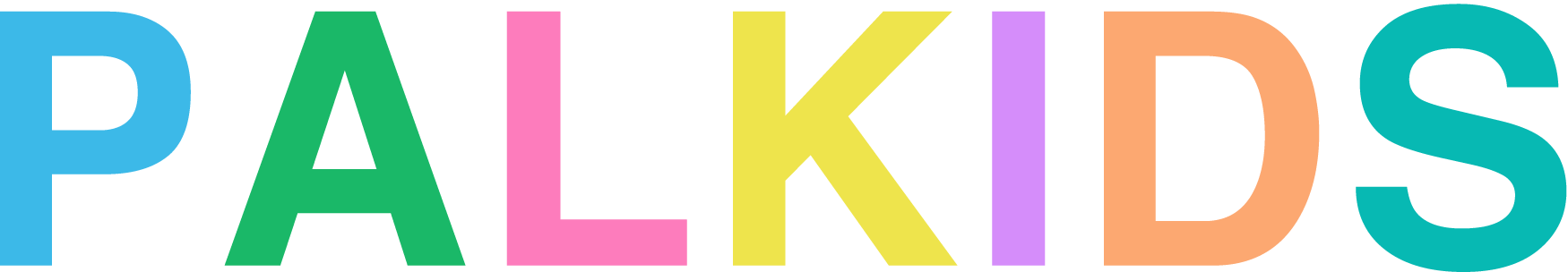パルキッズ通信 特集 | 日本の教育, 英語のリズム回路, 言語獲得, 言語獲得装置, 言語発達

2016年6月号特集
Vol.219 | ことばはリズムで身につけろ!
英語の四技能を学習すれば万事OK?
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
http://palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-1606/
船津洋『ことばはリズムで身につけろ!』(株式会社 児童英語研究所、2016年)
 我々は日常的に言語を使っていますが、特に日常的な会話なら、頭を悩ませたり深く考えたりしなくても、自然とことばを受け取り、また自然とことばを発します。もちろん言語の使い方に関しては、いろいろと考えることもあります。
我々は日常的に言語を使っていますが、特に日常的な会話なら、頭を悩ませたり深く考えたりしなくても、自然とことばを受け取り、また自然とことばを発します。もちろん言語の使い方に関しては、いろいろと考えることもあります。
たとえば、「この場合はこう言った方が良い」とか「今は黙っておいた方が良い」などなど、その人の性格や考え方、またはその場に居合わせる人が誰であるかなどの違いによって、話したり話さなかったり、話すにしても表現の仕方が変わったりします。
さらに重要なのは、同じ事象に出合っても、人によって反応が異なる点です。たとえば、イチゴが食卓に供される場面を想像してみましょう。大抵の人は「あ、イチゴだ」程度の脳の反応があり、そのまま口に運ぶでしょう。イチゴ好きであったり、特に食欲をそそるような立派なイチゴであれば、「おいしそうなイチゴ!」と口にするかもしれません。また、イチゴが嫌いな人だったら、黙って手を出さないこともあるでしょうし、「イチゴはどうも苦手で…」などと口にすることもあるかもしれません。たかがイチゴひとつでも、これだけの反応の差があるのです。これがもっと複雑な事情になれば、それこそ三者三様、十人十色、百人百様、千差万別です。
このように言語の使い方は様々ですが、それは思考や志向、もしくは嗜好等によって表に出てくる反応が異なるのであって、言語の根っこの部分、つまり相手の言うことを聞いてそれを理解するステップ、そして何かを言うステップにおいては、自動的に行われています。この自動的に行われる部分に関しては、人それぞれではなく、みんな同じ処理をしているのです。
母語について考えればわかりますが、情報に対する反応の多様性を除けば「聞いて理解」し、何かを「話す」、この2点においては無意識のうちに処理が為されています。
| 外国語と接すると
 このように、思考等を除いた言語の入出力は、自動的に処理されるのですが、外国語と出合うと、途端にこのような自動処理はできなくなります。
このように、思考等を除いた言語の入出力は、自動的に処理されるのですが、外国語と出合うと、途端にこのような自動処理はできなくなります。
英語を例に取ってみましょう。とはいっても、英語は、日本人にとっては世界に数千ある他の言語とは明らかに一線を画します。日本人は中学・高校で英語の文法知識とある程度の語彙を学んでいるので、英語がまるで未知の言語というわけではありません。その点は含んで考えないといけませんが、文法と語彙の知識があるという前提でもなお、英語を使いこなすことでができない理由は何でしょう。
答えはカンタン。入力系と出力系の言語機能を持っていないからです。
詳しくみて行きましょう。ある言語を聞いて理解する言語機能の入力系とは、どんな働きをするのでしょうか。まずは、聞き取ることが必要です。英語であれば、耳に入る文章を単語単位に切り出さないことには、何事も始まりませんので、まずこの作業が不可欠です。
英単語はその特徴として子音で終わることが多く、また前置詞や副詞などは母音で始まることが多いのです。そして、子音の後に母音が続けばリエゾンして、あたかもひとつの単語であるかのようにくっついてしまいます。このリエゾンは2単語間のみで発生するのではなく、母音で始まり子音で終わる単語が連続すれば、3語、4語がリエゾンして音の塊になってしまうことが珍しくありません。逆に、単語の中に音声の空白ができることもあるので、「音の切れ目=単語の切れ目」とは単純にはいかないのです。
これらの現象は、日本人が耳にした英語の文章から単語を切り出すための障害となっています。単語が発見できなければ、理解に繋がることもありません。
では、英語が聞き取れる、つまり耳に入る英語を単語単位で知覚できれば、理解できるでしょうか。なかなかそうはいきません。英単語は日本語の単語と完全には一致しておらず、意味も文脈によって変わってくるので、英単語一語に対して日本語一語を割り当てるやり方には限界があります。試しに、英和辞書で ‘get, have, take, run’ などの単語を探してみてください。ひとつの単語につき、どれだけの和訳があるのかに驚かされるはずです。やはり仮に単語を聞き取れたとしても理解できないことが少なくありません。
しばしば「日本人は英語を読めばわかるが、リスニングができない」などというご意見がありますが、それはまったくの誤解です。日本人は英語を聞き取れないのはもちろんのこと、単語単位に分かち書きされている英文を読んでも理解はできないのです。試しにペーパーバックでも何でも構いませんので、読んでみてください。サラっと読んで難なく理解できるようであれば、すでに英語を使いこなせているはずです。(注:専門的な知識を有する人が専門書を読むような場合は除きます。)
要するに、日本人は英語における入力系に関する言語機能(リスニング能力・リーディング能力)を持っていないのです。しかし、文法は知っているし、ある程度の語彙もある。これは何を意味するのでしょうか。
| 四技能を鍛える?
 世に「四技能」ということばがあります。リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4つです。そしてこれらをまんべんなく身につけることが、英語学習のゴールだという向きもあります。これはどういう考え方なのでしょうか。
世に「四技能」ということばがあります。リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4つです。そしてこれらをまんべんなく身につけることが、英語学習のゴールだという向きもあります。これはどういう考え方なのでしょうか。
すでに、日本人は聞き取りはほとんどできず、読解力も満足するレベルでないことはご理解いただけたと思います。
加えて、スピーキングやライティングに関して言えば、日本語を直訳することはできても、相手に通じないかもしれません。スピーキングの場合には、もちろん発音の問題もあるでしょうし、それ以前に日本語を直訳した文章では英語の体を為さないことも珍しくないからです。
それは文脈によって単語が意味を変えることも原因ですが、そもそも日本語と英語とでは発想が異なることにも起因します。文化が異なれば発想も異なります。日本のように「沈黙を金」とする文化と「喋らなければ居ないと同じ」と受け取られてしまうアメリカのような文化圏では、発想が異なるのは当然でしょう。発想が異なれば文章の作り方も違ってきます。
それを直訳できると仮定した上で、四技能に分割してそれぞれをトレーニングしましょうというのが、現在の学校英語の教え方です。
とはいえ、この学習方法を否定しているわけではありません。未知の言語に出合ったら、とりあえず自言語に解釈しないことには理解の糸口がつかめませんので、ある程度の文法知識と語彙をベースにして翻訳しながら、外国語を理解しようというのは、極めて自然なる人の営みです。
| 文法は重要?
 そもそも言語を使用するにおいて、どんな能力が必要なのでしょうか?まず、語彙は必要でしょう。ある単語が何を指し示すのかという知識が無ければ、たとえ聞き取れても読めても、理解には至りません。では、文法は必要なのでしょうか。
そもそも言語を使用するにおいて、どんな能力が必要なのでしょうか?まず、語彙は必要でしょう。ある単語が何を指し示すのかという知識が無ければ、たとえ聞き取れても読めても、理解には至りません。では、文法は必要なのでしょうか。
ちなみに、皆さんは日本語の文法をご存知ですか?たとえば「ゾウは鼻が長い」という文章のどれが主語かと尋ねられて、明快な答えを出せるでしょうか。
英文法の考え方をそのまま日本語に当てはめると、日本語の主語には「は」とか「が」が付きます。そしてそれらは微妙にニュアンスが異なります。「私は太郎です」というのと「私が太郎です」では、意味するところが異なりますが、日本語の母語話者であれば、この「は」と「が」の使い方を誤ることはありません。ただ、外国人にはこのあたりが難しいのです。
先の「ゾウは鼻が~」の文章に至っては、日本語の母語話者でも、どれが主語だか説明してくれと言われたら戸惑ってしまうのではないでしょうか。(詳細は三上彰先生の書籍をご参照願います。)
つまり、我々は日本語の文法を知らずに、日本語を使いこなしているのです。もちろん、学校で日本語の文法(らしきもの)も勉強しますが、それらの知識を元に日本語を正しく話せているわけではありません。日本語の文法を気にしながら発話している日本人は、相当まれでしょう。
さらに言えば、本当に文法など必要なのでしょうか?日本人は日本語の文法など知らないままに、数千年にわたり日本語を使ってきたわけです。また幼児の言語使用を見れば明らかなように、子どもたちは日本語の文法(ここでいう文法はいわゆる学校で習う文法のことです。)などまったく知らないうちに、日本語を使いこなしています。文法知識が無くても「は」と「が」を間違えることはないのです。しかし、幼児ですら無意識にできるようなことを、いざ説明するとなると、困難極まりないのです。さて、言語使用において、文法知識は本当に必要なのでしょうか。
| 先人に倣う
 日本は江戸時代に鎖国していましたが、中国(清)とオランダとは交渉がありました。中国の漢文に関しては、江戸時代から明治時代初期までに生まれたインテリたちは、広く嗜みとしてその運用力を有していたようです。もちろん我々が使っている漢字は中国伝来ですので、漢文を見てもまったく手がかりがないわけではありません。また語の並びに関しても、日本語とはまったく異なりますが、読み慣れていくうちに、自然と「ああこんな並びなんだな」と理解できるようになります。
日本は江戸時代に鎖国していましたが、中国(清)とオランダとは交渉がありました。中国の漢文に関しては、江戸時代から明治時代初期までに生まれたインテリたちは、広く嗜みとしてその運用力を有していたようです。もちろん我々が使っている漢字は中国伝来ですので、漢文を見てもまったく手がかりがないわけではありません。また語の並びに関しても、日本語とはまったく異なりますが、読み慣れていくうちに、自然と「ああこんな並びなんだな」と理解できるようになります。
そんなインテリたちも、蘭語(オランダ語)には手を焼いたようです。新井白石(江戸中期の学者)の流れから青木昆陽そして前野良沢、杉田玄白から大槻玄沢へと学問としての蘭学が発達していきます。(幕末にはもはや英語が主流であることが分かり、蘭語は急速に廃れてしまうのは残念ですが。)長崎の通事(通訳)たちは親子代々通訳ですのでオランダ語ができたようですが、現代のように飛行機や新幹線でひとっ飛び長崎に行って彼らに教えを請うわけにも行きません。オランダの本が手に入ると、それを辞書を片手に日本語に訳していくのです。
ところが、考えてみれば当たり前のことですが、辞書も最初からあるわけではない。誰かが作らなければなりません。江戸も末期になると辞書が作られていきますが、それまでの人たちは、例えば良沢にせよ白石にせよ手探りで翻訳していたようです。
そんな彼等の助けとなるのが、漢文の知識です。宣教師や貿易商人たちは、もちろん中国へも行くわけで、そこで蘭華(オランダ語-中国語)辞書が作られます。先にも述べたように、江戸期のインテリは漢文の素養があるので、この蘭華辞書を手がかりにオランダ語を日本語に訳していきました。そして、目の前の妙な語順の日本語を眺めながら、巧い具合に文章にしていったのです。
文法書もなかった時代ですから、さぞや大変だったことでしょう。しかし、文法書なしでも、繰り返し外国語に接しているうちに、そのことばのリズム・並びの法則のようなものが腑に落ちてくるのかもしれません。この様子は、幼児たちが語彙を少しずつ増やしながら、日々日本語に接するうちに日本語の並びの規則を発見するのと通底するように感じられるのは私だけでしょうか。
| 言語の持つリズムのようなもの
 私事で恐縮ですが、思うところあってラテン語を勉強中です。現在大学では中級まで進んだところですが、何とも手の焼ける言葉です。
私事で恐縮ですが、思うところあってラテン語を勉強中です。現在大学では中級まで進んだところですが、何とも手の焼ける言葉です。
ご存知の向きには釈迦に説法ですが、ラテン語の名詞には性・数・格があります。日本語の名詞は、例えば「友」であれば「友」で、この単語に性別もなければ複数形にして形が変わることもありませんし、格変化を起こすこともありません。しかし、ラテン語の場合には「友」を意味する ‘amicus’ は男性名詞で、複数になると ‘amici’ になり単数形/複数形それぞれに、主格(amicus / amici)属格(amico / amicorum)与格(amico / amicis)対格(amicum / amicos)奪格(amico / amicis)の語尾変化があります。つまりひとつの名詞が10通りの語尾を取るのです。
この変化がすべての名詞に共通してくれていればまだ助かるのですが、そうは問屋が卸してくれず、変化には5つの異なったパターンがあり、すべての単語はそのうちのどれかに属します。
また、名詞に形容詞をつけたければ、形容詞にはその名詞の性・数・格に合わせた語尾をつけてあげなくてはいけません。なお、動詞に至っては、3つの人称・単/複・6つの時制、さらに直説法・接続法・命令法・不定法・分詞があり、それらのほとんどに受動態がありますので、ひとつの動詞には140位の活用があり、さらには名詞同様に活用にも4パターンあるのです。…読んでいるだけで気鬱になりそうなので、もうこれ以上詳細には立ち入れません。
ラテン語の難点は、これらの活用をすべて覚えなくてはいけないことです(もちろんすべて覚えたわけではありません)が、良いところもあるのです。動詞が細かく変化するので、動詞を見れば主語がなくても何の話か解るのです。これは日本語や英語には無い感覚です。(日本語でも古典にはありますね。)
しかし、これが不思議なもので、ある程度の文法と単語を勉強した後、物語などを読み進めるうちに、なんとなく意味がわかってくるのです。文章とにらめっこしているうちに、ああ、なるほど、と腑に落ちる瞬間が少しずつではありますが、増えてきます。
今、ラテン語を話す人は一部のカトリック教会の聖職者さんたちだけですので、今後ラテン語会話に遭遇する機会は想うに皆無だと思いますし、会話を通してラテン語を上達しようと思ったとしても叶わないと思います。それでも、文章を読むことを通してですら、言語のリズムのようなものを感じられるようになってくるのは不思議なものです。
| 俳句
 このような、言語独特のリズムのようなものはもちろん日本語にもありますし、英語にもあります。それらがクッキリするのは会話よりも詩の世界かもしれません。
このような、言語独特のリズムのようなものはもちろん日本語にもありますし、英語にもあります。それらがクッキリするのは会話よりも詩の世界かもしれません。
英語の詩は、必ず韻(主に脚韻)を踏みます。マザーグースの詩などを見れば一目瞭然ですし、洋楽の歌詞を見てみれば、ロックであろうがポップスであろうがジャンルに関わらず、韻を踏んでいます。またシェイクスピアの詩などを見ればわかるように、音節の強弱を交互に持ってくることも同時に行われます。
それでは、日本語の詩はどうでしょうか。英語のように脚韻を踏むことは、滅多に行われません。滅多に、と書きましたが、ラップ音楽や一部の歌謡曲で押韻の試みは行われているようです。しかし、一般的ではありません。日本語の詩の中では、韻を踏むことよりも圧倒的に音数律が重要視されます。俳句や都々逸の、七五調や五七調などです。
英語では脚韻、日本語では音数律が、より重要な位置を占めている。つまり「リズム感」が英語と日本語では異なるのです。
最近、欧米では俳句が流行っているようですが、中身を見てみると「これが俳句か?」と首をひねってしまいます。
たとえば、松尾芭蕉の「ふるいけや かわずとびこむ みずのおと」を英訳すると、ドナルド キーン氏によれば “The ancient pond A frog leaps in The sound of the water.” となるそうですし、小泉八雲によると “Old pond Frogs jump in Sound of water.” などなど。他にも様々な著名人がこの俳句を英訳していますが、僕には芸術を味わう素養が無いのか、どうにもこれらの英詩がピンと来ません。
日本語で「ふるいけや~」と思い浮かべて、目をつむれば、その光景が浮かんできます。蛙の飛び込むかすかな音が周囲の静寂を際立たせる、そんな情景が浮かびます。ところが、英語に訳してしまうと、そんな俳句の奥深さが感じられないのです。逆もまたしかりで、シェイクスピアの詩も英語だからこそ味わえることもあるでしょう。日本語に訳してしまえば、意味はわかっても、その詩の先にある「なにか」までは伝わってこないのです。
| I(アイ)言語
 ここまで見てきたように、文法知識が無くても、言語に接しているうちに何となくその言語特有のリズムのようなものがわかってきます。また、そのリズムは言語間で異なり、俳句や英詩の間に見られるように互いに翻訳が難しく、意味は訳せたとしても、その奥にあるリズム感やそのリズム感から惹起される情緒などは、翻訳が極めて困難です。
ここまで見てきたように、文法知識が無くても、言語に接しているうちに何となくその言語特有のリズムのようなものがわかってきます。また、そのリズムは言語間で異なり、俳句や英詩の間に見られるように互いに翻訳が難しく、意味は訳せたとしても、その奥にあるリズム感やそのリズム感から惹起される情緒などは、翻訳が極めて困難です。
ところで、言語学の世界に「I(アイ)言語」(Internal言語)という概念があります。これは外の世界に音声(話された言葉)や文字(書かれた言葉)の形で表出された言語を表す「E 言語」(External言語)の対語として使われます。つまり、音声化や記号化される前の言語―ヒトの頭の中にあり、音声や記号を受け取ったときに理解したりイメージしたりしたものを言語に変換する言語機能―のことを「I 言語」と呼びます。
従来の「言語学」は ‘Philology’ と呼ばれていました。日本語では「文献学」とも言われます。読んで字の如く、文献から言語の変遷や本質を探る学問です。つまり、表出された言語(E言語)中心の学問です。そんな中から、規則性を示す文法が生まれ、さらにはそれらが外国語教育や外国語教授法と相まって「四技能」のトレーニングといった考え方が生まれてきたのかもしれません。
ただ最近(といってもここ数十年)は、「言語学」と言えばチョムスキー氏の発想に代表される “Linguistics” 的な研究がメインになりつつあるようです。その近代言語学(とでも呼べるもの)の中では、表出された現象としての言語の研究ではなく、「いかにしてヒトは言語を生み出すのか」「いかにしてヒトは短期間に言語を獲得できるのか」といった「I言語」の研究が盛んです。言語の構造や文法よりも、言語特有のリズムのようなもの、それが一体何であるのか、そんなテーマに関心が移りつつあるようです。
繰り返しになりますが、言語にはその言語特有のリズムがあり、それらは意外にも短期間で習得することができます。ヒトの頭の中には何らかの言語機能(言語学では、その初期状態を普遍文法、定常状態を個別文法と呼びます)があり、幼児の母語獲得や壮年のラテン語学習に見られるように、未知の言語に大量に接するとその機能が反応を起こし、その言語に内在するリズムのようなものの規則性を発見してくれるのです。
今回は少々ややこしい話になりましたが、言語に関する謎は尽きず、解明されていないものばかりです。
文法中心・四技能といった教授法に拘泥せず、ヒトの脳内にある言語機能を活用する学習法が深く研究され、広く実践されるようになれば、外国語習得にこれほど苦労することもなくなるのかもしれません。

船津 洋(Funatsu Hiroshi)
株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。