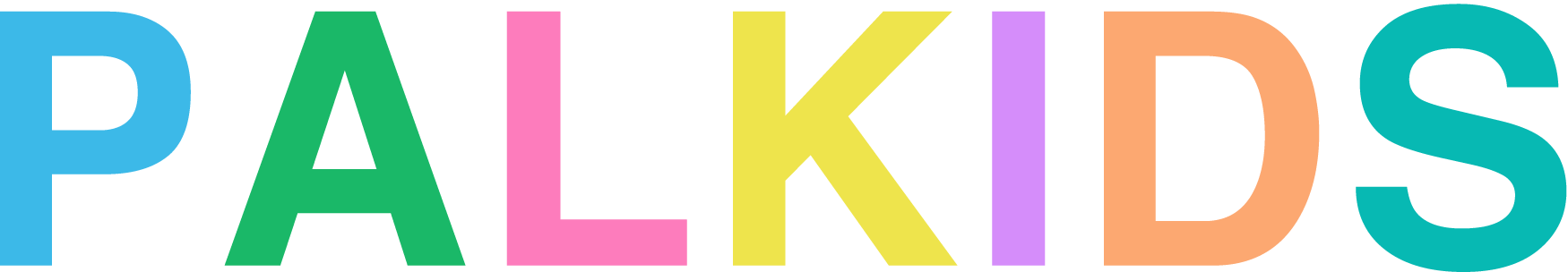パルキッズ通信 特集 | 多読, 第一言語習得, 英語環境, 言語獲得, 語彙

2016年7月号特集
Vol.220 | ことばと人間
当たり前すぎて気付かない?ヒトとコトバの不思議な関係
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
http://palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-1607/
船津洋『ことばと人間』(株式会社 児童英語研究所、2016年)
 「ことば」とは何とも不思議な代物です。言語学や心理学の世界では、「ことば」が先か、はたまた「概念」が先か等という議論が為されていますが、考えれば考えるほど面白い。世界には六千もの言語があるとも言われていますが、言語が変われば語彙も変わってきます。日本の言語学者・鈴木孝夫先生によれば、「虹」は日本語では7色ですが、英語では6色。これが、3色もあれば2色という言語もあるそうなのです。また、「太陽」も日本の子どもが描くと大抵は赤や橙色を使うのですが、英語圏だと黄色だそうです。「色」ひとつ取ってみても言語間でこれだけ異なります。ということは、人が母語を身につけると、その母語によって物事の見方が変わってくることになります。
「ことば」とは何とも不思議な代物です。言語学や心理学の世界では、「ことば」が先か、はたまた「概念」が先か等という議論が為されていますが、考えれば考えるほど面白い。世界には六千もの言語があるとも言われていますが、言語が変われば語彙も変わってきます。日本の言語学者・鈴木孝夫先生によれば、「虹」は日本語では7色ですが、英語では6色。これが、3色もあれば2色という言語もあるそうなのです。また、「太陽」も日本の子どもが描くと大抵は赤や橙色を使うのですが、英語圏だと黄色だそうです。「色」ひとつ取ってみても言語間でこれだけ異なります。ということは、人が母語を身につけると、その母語によって物事の見方が変わってくることになります。
また、幼児期の記憶に関して考えてみると、生まれたての記憶や1歳くらいの記憶があることは希ですが、2歳・3歳くらいから何となく記憶がある、という方も少なくないでしょう。ことばを獲得する前には、目の前の事象をどのように理解してよいのかわからないので、イメージが混沌としているが、一度言葉を身につけると、概念が理解され思考が整理されていき、その頃から記憶が残り始める…。そんな考え方もあるようです。
このように考えると、「ことばがあって初めて概念が存在する」という考え方が成り立ちそうです。
一方で、たとえば「川」といった概念は、日本語であろうが英語であろうが、未開の部族の言語であろうが、どの言語でも同じ認識が為されるため、言語以前に、物事の受け止め方に関する「人間に共通した処理の仕方」があるのではないかという考え方もあります。アメリカの言語学者・チョムスキー氏によるものです。これもこれで、なるほど、と唸ってしまいます。
いずれにしても、ことばを有することによって、ヒトは過去を記憶し未来を予想することができます。動物も学習はしますが、高が知れていて、ヒトの思考の複雑さには遙かに及びません。たとえば、蜂は「ダンス」として知られるような方法でコミュニケーションを取りますし、類人猿も音声や仕草でお互いにコミュケーションを取ります。しかし、それらは「エサがある」とか「逃げろ」といった意味と音声や仕草の対応で、せいぜい数十の組み合わせに過ぎません。
ところが、ヒトの言語はまったく次元が異なります。専門的には「離散無限性」がその特徴なのですが、簡単に言えば、日本語のひらがなや英語のアルファベットで象徴される有限個の音素の組み合わせよって作られた有限個の語によって、無限の組み合わせが可能であることを意味します。
たとえば、私が今エディターに打ち込んでいるこの文章は、おそらく人類史上初めての組み合わせで行われています。つまり、たったこれだけの文でも、今までに同じこと(同じようなことではなく完全に一致すること)を書いたり口にしたりした人は、おそらく居ないのです。また、「太郎がリンゴを食べた」という文章も、これを「花子が」~「と言った」で挟むこともできるし、さらに「と私は聞いた」を最後に加えたり、またさらに「と記憶している」と付け加えたりすることもできます。このように、際限無く文章を長くしていくこともできるので、「世界最長の文」というのは理論上存在しないことになります。このような離散無限性を有するという点で、明らかに他の動物のコミュニケーションとは異なります。
| 言語はコミュニケーションのためのもの?
 言語は、コミュニケーションの道具として使われることもありますが、それは言語使用のほんの一側面に過ぎません。アメリカの心理学者・メラビアン氏によれば、コミュニケーションにおいて、音声メッセージの内容(言語)自体の占める割合は7%に過ぎません。また、文中の特定の箇所に付けたアクセントや、あきれた感じ、感心した感じなどを表すパラ言語情報、話し手の声からわかる性別や年齢、健康状態などの非言語情報が38%、そして見た目や身振り・手振り、視線などの直接音声言語とは関係のない仕草がコミュニケーションにおいて55%もの割合を占めています。
言語は、コミュニケーションの道具として使われることもありますが、それは言語使用のほんの一側面に過ぎません。アメリカの心理学者・メラビアン氏によれば、コミュニケーションにおいて、音声メッセージの内容(言語)自体の占める割合は7%に過ぎません。また、文中の特定の箇所に付けたアクセントや、あきれた感じ、感心した感じなどを表すパラ言語情報、話し手の声からわかる性別や年齢、健康状態などの非言語情報が38%、そして見た目や身振り・手振り、視線などの直接音声言語とは関係のない仕草がコミュニケーションにおいて55%もの割合を占めています。
このように、コミュニケーションにおける言語使用の比率は極めて少ないのです。では、私たちは言語を使って他に何をしているのでしょうか?実は、そのほとんどを「思考」に使用しているのです。しかも、思考といっても話をしたり、文章を書いたりという生産的な思考ばかりではありません。ほとんどは「なぜあんなことを言ってしまったのか」といった後悔など自責の念、または未来への心配などなど、自らを苦しめるために使われているのです。もちろん生産的な使用もしますが、言語は自分を苦しめるためにヒトに与えられた能力とも言えそうです。ヒトはコミュニケーションを取るために言語を身につけた、という考え方は少々怪しいですね。
生物は環境適応のために進化するという考え方もありますが、進化と呼ばれる現象は偶然の突然変異によってもたらされます。もし必要に迫られて進化するのであれば、山岳地帯に住む人間にはもうそろそろ翼が生えても良い頃でしょうし、水上生活者にはエラや水かきがもたらされても良いことになってしまうでしょう。
| 突然変異から生まれた言語
 言語は、10万年もしくは6〜7万年前、あるひとつの個体に起きた突然変異によってもたらされた、と現在では考えられています。とある一人の赤ん坊が突然言語を持ったのです。ただ、親は「ウホウホ」言っています。もっとも、声帯から口蓋、舌、鼻腔などの構音構造はおそらく現在の人間と同じですので、我々と同じようにバラエティーに富んだ音を生産することができたのでしょう。しかし、言語がないので当面ここでは「ウホウホ」としておきましょう。
言語は、10万年もしくは6〜7万年前、あるひとつの個体に起きた突然変異によってもたらされた、と現在では考えられています。とある一人の赤ん坊が突然言語を持ったのです。ただ、親は「ウホウホ」言っています。もっとも、声帯から口蓋、舌、鼻腔などの構音構造はおそらく現在の人間と同じですので、我々と同じようにバラエティーに富んだ音を生産することができたのでしょう。しかし、言語がないので当面ここでは「ウホウホ」としておきましょう。
そして、その赤ん坊は大きくなるにつれ、少しずつ思考を整理整頓していきます。ただ、親が「ウホウホ」ですので、その子は残念なことに豊かな語彙を持つことができません。ただ、今度はその子が親になります。するとその子どもたちも、遺伝子に「言語」に関わるプログラムを持つことになります。すると、結婚相手である子どもたちの父親は「ウホウホ」でも、母親(先に突然変異した赤ん坊)とその子どもたちは言語という共通のツールを持つことになります。このあたりで、「母ちゃん(父ちゃん、でももちろん差し支えありません)、私らは他の人と違うね」と感じるかもしれません。
この言語を持った家族は、様々な概念を整理する術を持っていて、過去の記憶をたどり、未来を想像することができます。自然と、言語を有さない他のグループより狩猟や採集においても秀でることになるでしょう。自分を養ってくれそうなところにヒトは集まってきますので、この言語を持った種が繁殖していくのも想像に難くありません。そして、そのグループが環境に適応した種として繁栄し、アフリカを出てオセアニアへ向かい、さらに世界中に広がっていったと考えられているのです。つまり、我々人類すべては一人の親から派生している、同じ遺伝子を持った家族とも言えます。
| 音声から文字へ
 ヒトが「文字」を持つようになったのは、紀元前数千年に遡りますが、それでも言語使用の歴史から見れば「つい最近」といえます。更新世末期(12万年~1万1700年前)、日本列島が大陸と陸続きの時に、現人類がこの島にやってきて、1万年前までには大陸から切り離され日本人の祖先になりました(もちろんその後も大陸や半島から、折に触れ大量の人口が流入しました)。
ヒトが「文字」を持つようになったのは、紀元前数千年に遡りますが、それでも言語使用の歴史から見れば「つい最近」といえます。更新世末期(12万年~1万1700年前)、日本列島が大陸と陸続きの時に、現人類がこの島にやってきて、1万年前までには大陸から切り離され日本人の祖先になりました(もちろんその後も大陸や半島から、折に触れ大量の人口が流入しました)。
そんな私たちの祖先が発展させてきたのが「大和言葉」ですが、文字はずいぶん最近まで持たなかったようです。弥生時代末期になると「卑弥呼」や「倭国」などの記述が見られますが、それらはあくまでも中国の書物に残るものであって、表記としての日本語はまだ成立していません。しかし、古墳時代中期(5世紀頃)あたりから稲荷山古墳(埼玉県行田市)の鉄剣に見られるような文字が確認されるようになります。おそらく仏教の伝来とともに漢字が伝わり、それを日本の大和言葉に当てる万葉仮名や草仮名のような使い方が広がり、平安時代の早い時期(9世紀頃)には平仮名・片仮名が作られ、漢字とともに使われるようになりました。
不思議なもので、ほぼ時を同じくして遙か彼方のブリテン島でも、6世紀頃にゲルマン人とともに(古)英語の時代が始まります。文献の残る6世紀頃の古英語を見ると、今の英語の感覚ではちょっと理解しがたい英語です。1066年のノルマン征服により、上流階級(貴族)がフランス語を使うようになると、その影響を受けた中英語時代が始まります。その後、中英語末期の16世紀、母音が一斉に変化した「母音大推移」から現代英語へと変化しました。シェイクスピアの時代、日本史でいえば織豊時代から大坂の陣に当たる頃です。こうした英語の変化や規則性を、残された文献から探る言語学が ‘Philology’(文献学)と呼ばれます。
| ザックリわかる「現代言語学の歴史」
 先月号でもわずかに触れましたが、言語学は外界へ産出された言語、その中でも主に文書として残っている物を研究する学問から始まりました。そんな学問を元にして、現在の英語学や英語教育法が編まれてきたのです。これは極めて科学的な方法です。一方で、既に述べたように、言語は主に思考において使用されるのですから、文献からの研究はいかに膨大な量の言語証拠をかき集めたとしても、ヒトの頭の中で行われていることの一部分を取り扱っているに過ぎません。
先月号でもわずかに触れましたが、言語学は外界へ産出された言語、その中でも主に文書として残っている物を研究する学問から始まりました。そんな学問を元にして、現在の英語学や英語教育法が編まれてきたのです。これは極めて科学的な方法です。一方で、既に述べたように、言語は主に思考において使用されるのですから、文献からの研究はいかに膨大な量の言語証拠をかき集めたとしても、ヒトの頭の中で行われていることの一部分を取り扱っているに過ぎません。
ところが、1950年代以降、この言語学の流れが変わってきています。前出のチョムスキー氏による「E言語(External言語:口にしたり書いたりされた言語)は無限なのでそれらすべてを研究することはできない。従ってそれらを生み出す仕組み=I言語(Internal言語)の方を研究しよう」という考え方です。氏の仮説によれば、ヒトの脳内には「普遍文法」という言語の初期フォーマットが遺伝的に存在して、その普遍文法に、母語をはじめとする言語情報を与えることで、個別文法(つまり日本語なり英語なりの言語)へと育っていくというのです。
ただ、この考え方ではなかなか解決しきれない問題が出てきました。幼児の言語獲得です。言語を整理していくと、ずいぶん豊富な量の「ルール」に行き着きます。平叙文だけでも、動詞の種類によって二重目的語を取る、目的語と補語を取る、目的語と前置詞句を取るなどの規則があり、文章が複雑になるほどルールも多くなります。さらに疑問文の作り方も、ひとつやふたつではありません。そのような膨大な量の文の構造に関する知識を、どうして赤ちゃんが、母親によって与えられる極めて限定的で不完全な文章から、しかもわずか数年間で、得ることができるのか?という大きな疑問が立ちはだかるわけです。これは「プラトンの問題」とも呼ばれています。
さて、その後80年代になると、「普遍文法」にはすべての言語に共通するいくつかの「原理」(単語を繋いで句を作る、重要な部分は句の真ん中ではなく両端に現れる、といったルール)と、言語間において差がある「パラメータ」(複数形があるか、名詞に性があるか、主要部がどこに現れるか、疑問詞が移動するか、といったルール)があり、そのパラメータ値の設定だけで、英語になったり日本語になったりする、という仮説が提唱されます。
「パラメータ」の例を挙げてみましょう。
・句の主要部の位置:日本語の場合には句の後尾に現れるのに対して、英語の場合には句の先頭に現れます。たとえば英語の前置詞句では句の性格を決定する前置詞は “to school / at home / in suits” のように先頭に、日本語では(英語の前置詞に対して後置詞と捉えます)「学校へ / 家で / スーツで」のように末尾に現れます。
・疑問文の作り方:日本語の場合には疑問詞は移動しません(「彼はリンゴを食べます」→「彼は何を食べますか」)が、英語の場合には文頭に移動します(”He eats apples.”→”What does he eat?”)。また、日本語では疑問詞が移動しない代わりに、疑問の終助詞(「~か?」など)が文末に現れます。これもパラメータのひとつだというわけです。
幼児たちは身の回りにある言語情報をもとにして、これらのパラメータ値の「スイッチ」をパチパチと入れていき、その結果、日本語や英語ができあがるというような考え方です。
ただ、この考え方も今世紀になって研究が進めば進むほど、パラメータの数が多くなりすぎる、もっとシンプルな考え方はないのかと言われ始めました。「ミニマリスト・プログラム」とも呼ばれる考え方です。この考え方では、極端に「ひょっとすると言語には併合(単語をつなげること)しかないのではないか?」というところまで来ています。
ただ、まだまだ道半ばの感は拭えません。頭の中で行われていることを可視化することはできませんから、当然でしょう。ただ、間違いなく従来の言語学・文献学 ‘Philology’ の枠からは抜け出して、ヒトの言語産出の「仕組み」に迫りつつあることは間違いありません。
また一方で、すでに認められていることもたくさんあります。たとえば、「言語獲得は学習の延長にあるのではない。獲得と学習とはまったく別物である」というアメリカの言語学者・クラッシェン氏の考え方などは、欧米の外国語教授法では広く受け入れられています。「習うより慣れろ」といった考え方です。
もちろんこれには前提があって、何でも良いから慣れる=入力するのではなく、理解できる範疇より少し新しい情報を継続的に入れ続け、理解の幅を自然に徐々に広げていくのです。言うなれば、従来の「文法を教える」教授法ではなく、言語情報に触れることによって自然と「獲得させる」という方法です。この中心にあるのは、チョムスキー氏の言う「ヒトには普遍文法が遺伝的に備わっていて」「周囲の言語刺激がそれを(日本語、英語などの)個別文法へと育て上げてく」という考え方です。
今回は、言語と言語学の歴史についての最新情報をお伝えしました。いまだわからないことばかりの「言語」ですが、ひとつだけ言えることは「外国語学習においての定説はない」ということでしょう。つまり、学校での英語教育をはじめとして「これで必ずできるようになる」という学習法は定義されていないのです。
その中で確率論的にいえば、日本の学校で行われてきた英語教育は、成功率としてはあまりにもお粗末と言わざるを得ません。日本人の多くがそう考えていることが、日本人の「英会話信仰」に繋がるのでしょうし、早期の英語教育熱へと多くの人たちを導くのでしょう。ただ「英会話」の練習から英語を獲得したという話もあまり聞きません。どうやら英語獲得に成功した人たちに共通しているのは「大量の英語に触れた」ということのみかもしれません。そして、その大量入力を可能にするのは、幼児期ならば、物理的に考えて(理解可能な範囲内の)英語の音声の耳からの入力しかありませんし、耳からの入力の臨界期を過ぎた年齢になれば多読しかないのです。

船津 洋(Funatsu Hiroshi)
株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。