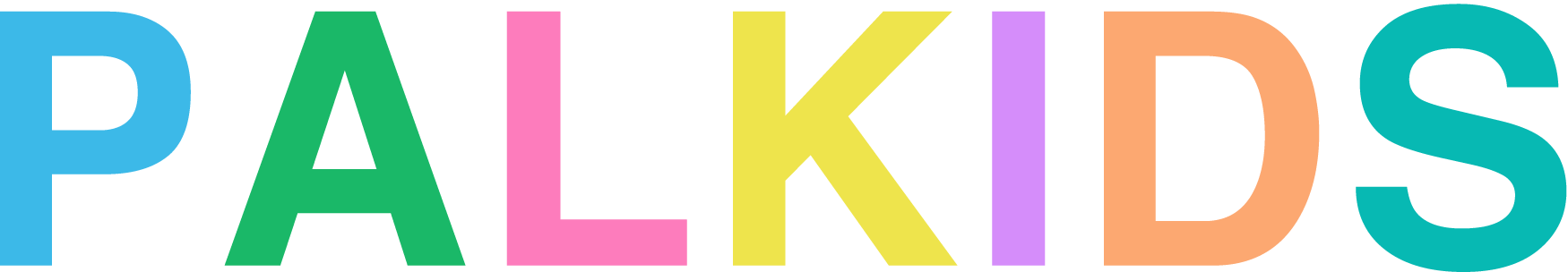2023年6月号特集
Vol.303 | 留学せずに英語を身につける方法
正しく読んで「英語の閾値」を超えよう
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-2306/
船津洋『留学せずに英語を身につける方法』(株式会社 児童英語研究所、2023年)
 右手で左手の甲を軽く叩いてみてください。「痛い」とは感じないでしょう。それでは、少しずつ勢いを増していき、徐々に強く叩いてみてください。かなりの勢いが必要になりますが、パシっと叩いた瞬間に「痛い」と感じる強さがあります。それが閾値です。
右手で左手の甲を軽く叩いてみてください。「痛い」とは感じないでしょう。それでは、少しずつ勢いを増していき、徐々に強く叩いてみてください。かなりの勢いが必要になりますが、パシっと叩いた瞬間に「痛い」と感じる強さがあります。それが閾値です。
人の耳で聞き取れる音の範囲は、20Hz(ヘルツ)から20,000Hzくらいです。若い人だと20,000Hzは聞こえますが、歳をとるとだんだん耳が遠くなってきます。僕は10,000Hzは聞こえますが11,000Hzだと聞こえなくなります。ただ、これはスピーカー経由なので様々な雑音が入ります。せっかくなので、AirPods Pro(イヤフォン)でボリュームを最大にして聞いてみると14,000Hzまで聞こえました。ただ、その上は聞こえません。ここに閾値があります。
閾値とは、とある刺激を受けた時にそれを知覚できる最小限の強度のことです。つまり、痛いか痛くないか、聞こえるか聞こえないかの境界に閾値があるわけです。これは境界を意味する「敷居」と考えて良いでしょう。
言語にも閾値があります。言語は習得したか否かに分かれます。
これには少し説明が必要かもしれません。言語には様々なレベルがあります。幼児たちの語彙は乏しく、理解できる範囲も広くはありません。彼らは成長するにつれて、語彙を豊かにして、理解力も高くなってきます。この段階は「痛いか痛くないか」とか「聞こえるか聞こえないか」といった二値で図ることはできません。習得には様々な段階があります。
しかし、それ以前の段階として、幼児たちは母語を聞き取って直感的にイメージする能力を身につけています。聞き取ろうとしなくても単語単位で聞こえてしまい、理解しようとしなくても直感的にイメージ(あるいは理解)できるようになります。
この点、「聞き取れて直感的に理解できるか否か」という習得段階は二値です。つまり、閾値を超えて習得できているか、あるいは閾値を超えずにいるか、に分けることができます。
少しずつできるようになるのではなく、できるかできないかの二値
 僕は高校時代に米国に留学しましたが、渡米から4ヶ月ほど経ったある日に、この閾値を超えたようです。ある朝起きてみると、ホストファミリーの交わす英語が、まるで日本語のように「聞こうとしなくても聞こえ」「分かろうとしなくても分かる」ようになりました。
僕は高校時代に米国に留学しましたが、渡米から4ヶ月ほど経ったある日に、この閾値を超えたようです。ある朝起きてみると、ホストファミリーの交わす英語が、まるで日本語のように「聞こうとしなくても聞こえ」「分かろうとしなくても分かる」ようになりました。
分からない語も、理解できないフレーズもたくさんあります。もちろん、聞き取り能力もそれほど優れたものではありません。しかし、どの部分が聞き取れないのか、あるいはどの語が分からないのかが「分かる」のです。
これは、1歳半から2歳くらいで、日本語を聞き取れるようになり、同時に直感的に日本語を理解できるようになった日本人の幼児たちが、そこから日本語を上達させていく過程と似ています。彼らは、汚れるを「よぼれる」、エイブラハムの子が「1人はよっぽであとはちみ」、反復でなく「パンプ君横跳び」のように、日常的な聞き間違いや、勘違いを経て日本語を上達させていきます。
さて、世に溢れる英語学習法ですが、ちょっと調べてみただけでいくつもの「(こうすれば英語が)できる」という方法が見つかりました。
「英語を話したければ…」「○語でペラペラに」「簡単に英語を話せる方法」「本物の英語を話せるように」「スピーキングのコツ」「全く新しい英語学習法」「伝わる英文の作り方」「リズムが重要」「1日3分」…などなどです。
さらには、「英語学習には合う合わないがある」とか「様々なやり方がある」ようですが、幼児が日本語を身につけたり、留学生が英語を身につけたりするように、言語を身につける正しい方法には「合う合わない」など存在しません。同時に言語を身につけるには「様々なやり方がある」のですが、間違ったやり方ではいくらその人に「合う」学習法でも一向に身につかないでしょう。
幼児たちにとっての日本語や、留学生にとっての英語のように、聞き取ろうとしなくても聞こえてしまい、分かろうとしなくてもイメージ・理解できてしまうような英語力を身につけるためには、大量のインプットが必要です。ちょっとしたコツを記憶することや、わずかなインプットでは、その目標は達成できないのです。
また、徐々に英語ができるようになることもありません。英語を身につけた方ならお分かりと思いますが、英語は「少しずつ身について」くるのではなく、夢中でインプットしているうちに「気づけば身についている」のです。
インストール完了か失敗か
 この点は、『パルキッズ通信』4月号や5月号で触れていますが、コンピュータに例えれば、英語というOSはインストールできたか、そうでないかであり、「半分インストールできたので半分使える」などということはありません。
この点は、『パルキッズ通信』4月号や5月号で触れていますが、コンピュータに例えれば、英語というOSはインストールできたか、そうでないかであり、「半分インストールできたので半分使える」などということはありません。
もちろん、挨拶や決まり文句を学べば、そのフレーズがそのまま出てきた時には聞き取れるかもしれません。たくさんの英単語を知っていれば、ランダムに耳に入る英文の中で聞き取れる語は増えるでしょう。しかし、それと英語を聞き取れるということは異なります。
幼児たちは、おそらく千語程度しか理解できる英単語がなくても、英語を聞き取ることができます。すでに述べたように、何が聞き取れないか、何が分からないかが分かるのです。これが、英語を聞き取れるということです。
英語ができなかった者が、気づけば英語を聞き取れる・理解できるようになっている点に関して、多くの帰国子女たちは、習得時期の年齢が低い ‘early learner’ であるので自覚しにくいでしょう、また、幼児期に二か国語を習得してしまっている ‘simultaneous bilingual’ や ‘sequential bilingual’ と呼ばれるバイリンガルたちは、尚更自覚できません。
また、言うまでもありませんが、英語を身につけていない人たちには、この「英語習得には閾値がある」という感覚は理解できないでしょう。
すると、この閾値を感じることができるのは、あるいは思い返せば「いつの間にか聞こうとしなくても聞こえ、分かろうとしなくても理解できる」ようになっていたことを感覚として理解できるのは、’late leaner’ である留学生か、海外経験無くして英語を身につけてしまった「純ジャパ」に限られてくるでしょう。加えて、英語学習法や言語学に関心がなければ「どうやって身につけたか」などに思いを馳せることもないでしょう。
その点、どうやら僕は「英語の閾値」について語る資格がありそうです。
日本語と英語は遠い
 日本人にとっての英語の習得は、困難を極めます。音声や音韻の側面から見ると、英語と日本語では、音素の種類も違えば音節構造も異なります。またプロソディー(韻律)やアクセントも違います。
日本人にとっての英語の習得は、困難を極めます。音声や音韻の側面から見ると、英語と日本語では、音素の種類も違えば音節構造も異なります。またプロソディー(韻律)やアクセントも違います。
統語面からみても、真逆と言って良いほど異なる言語です。日本語には複数形や三単現の区別がありませんが、英語にはそれらの区別があります。日本語には単複両方において冠詞が必要ではありませんが、英語では要求されることもあります。また、日本語では代名詞を省略して言わないことが普通に行われます(pro-drop言語)。それどころか、主語すら口にしないことも珍しくありません。
語の並べ方も、まったく異なります。英語は主要部が左側ですが、日本語は右側です。例えば、目的語がある場合、英語では首部の動詞が現れてから目的語が現れます。日本語では目的語の後ろに動詞がきます。同様に、英語では主要部の否定辞が述部の左側に現れるのに対して、日本語は右側に現れます。つまり、日本語は文を最後まで聞き終わらないことには、その文が肯定文なのか否定文なのか区別がつきません。
それゆえに、「後ろから訳せば良い」などという人もいます。確かに、逆から訳すと日本語の文法に近づきます。しかし、英語を話す人は、思いついた語を逆から並べているわけではありません。彼らからすれば、最初から日本語とはまったく逆に見える語の並びが頭に浮かんでいるのです。
このように、日本語と英語はずいぶんと遠く離れた言語です。
英語を身につけるということは、英語の語順で理解できる、また作文できることを意味します。訳して考えながら語を並べているうちは、英語を身につけたとは言えないのです。
幼児の言語習得と同じ
 言語の習得に関しては、チョムスキーの提案している「普遍文法」なるものが存在するという考え方があります。
言語の習得に関しては、チョムスキーの提案している「普遍文法」なるものが存在するという考え方があります。
この理論はスッキリしています。そこでは、ヒトには生まれながらにして、言語に関するかなりの知識を持っていて、あとは生まれてから「音素や音韻知識」を帰納的に学習して、いくつかの「パラメータを設定」すれば一丁上がり、とされています。パラメータの設定とは上で述べたような、主要部が最初に来るか最後に来るか、複数形の有無、三単現の s の有無、冠詞の有無などです。
この考え方に基づくと、パラメータの設定が済めば、それが日本語なり英語なりの個別言語として働き始めることになります。幼児はこの要領で母語を身につけていくとされています。
しかし、「言語を身につける」といっても、そうは問屋が卸してくれないこともあります。
僕などの留学生のケースでは、OSのインストールとしての言語習得が済んだ段階、つまりある程度以上は英語を聞き取れて、直感的に理解できる能力を身につけたあとも、冠詞や単複を間違えたりします。パラメータの設定で脳内に言語が構築されるのであれば、そのような間違いは起こりません。現に、英語ネイティブたちは冠詞や単複を間違えることはありません。
しかし、留学生は間違えます。思春期以降に外国語を身につける ‘late learner’ の留学生ばかりではありません。思春期以前に外国語を身につける ‘early learner’ にしても、文法ミスはあります。
さらに、リスニングに関しても、留学生のみならず帰国子女でも、聞き間違いや、正しく聞き取れないことがままあるのです。
このように考えれば、留学生たちは、幼児が母語を身につけるのとは少し違った言語の身につけ方をしていると考えなくてはいけないことになります。おそらくはディープラーニングのような類推、帰納、パターン学習などの計算を用いて言語を身につけているものと考えられます。
もちろん、そのために大量の情報インプットが必要であることは言うまでもないでしょう。
この点に関しては、『パルキッズ通信2022年1月号』でも触れているのでご確認ください。
このあたりは言語学者に任せるとして、いずれにせよ、ヒトは言語を身につける能力を持っているのです。
そして、普遍文法を使って身につけなくても、留学生や帰国子女、あるいは純ジャパのように大量の英語のインプットがなされれば、脳というコンピュータが英語を学習してくれるわけです。
英語以外のケース
 英語を身につけたいのであれば、留学するのが一番手っ取り早いのは自明でしょう。しかし、すべての人が留学できるわけではありません。では、日本国内に居ながらにして英語を身につけることは可能なのでしょうか。
英語を身につけたいのであれば、留学するのが一番手っ取り早いのは自明でしょう。しかし、すべての人が留学できるわけではありません。では、日本国内に居ながらにして英語を身につけることは可能なのでしょうか。
もちろん可能です。少ないながらも存在する「純ジャパ」は、海外経験なくして英語を身につけています。
それでは、彼らはどのようにして英語を身につけるのでしょうか。
それも簡単。大量のインプットから英語を身につけています。
ここで、もうひとつ僕の体験を披瀝しましょう。
僕は大学院入試のために外国語を勉強しました。もともとラテン語を勉強していたのですが、第二外国語にラテン語の試験がない大学院へ進学するので、何らかの第二外国語が必要となったわけです。
英語は問題ありませんし、ラテン語もある程度は分かります。そんな僕が大学院入試用に選択すべき第二外国語は、フランス語一択でした。
理由は簡単です。現在の英語の語彙のうち、英語オリジナルのものは20%ほどです。残りの8割はフランス語とラテン語からきています。つまり、英語とラテン語を知っていれば、フランス語に関しては、すでにかなりの知識を持っていることになるのです。
さて、余談はさておき、受験用のフランス語についてです。
大学院受験で要求される第二外国語のレベルは、英検で言えば3級から準2級程度です。初級ではなく中級くらいです。大したことはない。しかも、リスニングやスピーキングは課されません。
そこで、僕は最初にフランス語の入門の文法書を1冊、軽く読み流しました。その後チューターをつけて、徹底的に読むことにしました。週1回90分で、内容はテキストの音読と和訳です。まず僕が一行読んで、続けて先生に読んでもらい、間違えている発音を直します。そして日本語に訳していきます。
外国人大学生の二外学習用のテキストから始まり、子ども向けのニュースサイトを片端から読んでは訳していきました。
面白いことに、最初は日本語に訳して理解していましたが、半年も経たないうちに、英語に訳した方が理解が早いことに気づき、それ以降はフランス語を見ると自然と英語に変換されるようになります。
そして、さらに半年も経つころには、英語に訳すこともせずに、フランス語をそのまま理解できるようになりました。主語と述語、あるいは目的語などの文の主要要素が直感的に分かるようになり、その周辺情報も読み取れるようになりました。
いやはや、不思議です。もちろん、複雑な文はまだ理解できませんが、何と言っても語が英語やラテン語と共通しているので、テレビのニュースの字幕なども何となく理解できるようになりました。アラ還のおじさんのポンコツ頭でも新しい言語を学べるのだと、励みになります。
純ジャパに学ぶ
 さて、このようにしてフランス語が「書いてあれば」何となく分かるようになったわけですが、これは大量にフランス語の文を読んだから得られた能力に他なりません。しかし、大量と言っても週に千語とか二千語です。辞書をひいたり参考書に当たったりする時間を含めても、2~3時間もあれば読んで理解できる量です。大した量ではありません。
さて、このようにしてフランス語が「書いてあれば」何となく分かるようになったわけですが、これは大量にフランス語の文を読んだから得られた能力に他なりません。しかし、大量と言っても週に千語とか二千語です。辞書をひいたり参考書に当たったりする時間を含めても、2~3時間もあれば読んで理解できる量です。大した量ではありません。
しかし、このようにフランス語を「読んで理解」できるようになった僕ですが、「聞いて理解」できるところまでは到底到達していません。当然です。僕のフランス語のチューターは日本語ペラペラで、テキストに書いてある文以外はすべて日本語でやりとりしていました。ランダムなフランス語などまったく聞いていないのですから、リスニングができるようになるわけもありません。
このように、中途半端にフランス語を身につけたわけですので、これからは大量にリスニングすれば読んで理解できるばかりでなく、聞いても理解できるようになることでしょう。まだ、その点に関しては手をつけていないので、しっかりフランス語が身についたら改めてご報告することにします。
しかし、純ジャパと呼ばれる猛者たちは、英語を読んで理解できるばかりでなく、耳から入る英語も直感的に理解できるようになっているわけです。
上記のようにフランス語を身につけた感覚から言えば、大量に読み続ければ直感的に読んで理解できるようになりますが、聞き取りの方も聞き続けるだけで良いのでしょうか。
そこで、この点について純ジャパに聞いてみたところ、どうやら大量に英語に接しているうちに、最初は読んだ英文を日本語に訳さずに理解できるようになり、それに続いて耳に入る英語を直感的に聞き取って理解できるようになったようです。
いずれにしても、たくさん読んで、たくさん聞くことがインプットとなり、英語、あるいは英語以外の言語を身につけていくことは間違いありません。
外国語の音の学習
 人間が、母語や外国語に限らず、どのようにして言語を身につけていくのかを見ていくと、子どもは耳からのインプットで普遍文法なりディープラーニングで、大人は目からのインプットを中心にディープラーニングで、言語を習得していることがわかります。
人間が、母語や外国語に限らず、どのようにして言語を身につけていくのかを見ていくと、子どもは耳からのインプットで普遍文法なりディープラーニングで、大人は目からのインプットを中心にディープラーニングで、言語を習得していることがわかります。
さて、ここで外国語の「音」に目を向けることにしましょう。
母語なり外国語なりの音の習得、音声や音韻などの知識の習得は帰納的に行われるようです。これは幼児でも大人でも変わりません。
この件に関して、幼児の場合には何の問題もありませんが、大人の場合にはひとつ重大な問題があります。
そうです。大人は外国語を聞き取れないのです。幼児は耳が良いので、外国語を耳にしても母語との違いを微妙に聞き分けて、外国語の音を真似るようになります。そして、見事なまでにうまく発音できるようになります。
しかし、大人の場合にはそうはいきません。
いくら真似てみても、一向に英語の音声らしくならない。その点で悩んでいらっしゃる方も少なくないでしょう。それが証拠に、最近の大人の英語学習は、英会話から音の学習へとトレンドが変化しているように思えます。
これは、喜ばしいことです。なぜならば、大人の場合には単なる耳マネでは正しい英語の発音ができないのです。そして、正しく発音できないのであれば、聞き取れるようになる由もありません。
ただ、少し残念なのは、大抵は音の違いに着目するばかり、つまり音声の学習ばかりで音韻の学習まで言及しているところが少ない点でしょう。
この点に関しては、後でもう一度触れることにします。まずは、正しい発音がリスニング能力の向上とどのように関係しているのかを見ることにしましょう。
モーター理論
 なぜ、英語を正しく発音できることが、リスニング力の向上につながるのでしょうか。
なぜ、英語を正しく発音できることが、リスニング力の向上につながるのでしょうか。
正しく聞き取れれば、正しく発音できることは何となくわかります。しかし、その逆がどのように成立するのか考えてみることにしましょう。
英語は正しく聞き取れないことには、正しく発音することができません。勘とか雰囲気で発音している分には、相手に伝わる英語にはなかなか到達できません。逆に、正しく聞き取れれば、正しく発音できると考えることができます。
モーター理論という考え方があります。これは、人は聞き取った音声を無意識のうちに自分の口の中で再現しているという観察から生じています。どうやら、音を聞き取るときには、単に聞くだけでなく、口の中でその音を再現しているようなのです。
これに関しては、『パルキッズ通信2022年12月号』で詳しいので、そちらをご参照ください。
さて、それでは、なぜ正しく発音することがリスニング能力の向上につながるのでしょうか。
正しく発音できるということは、その自分の発した音声が外耳から内耳を通して聞き取られるようになります。これが正しい音であれば、あるいは正しい音に近ければ、次にその音を聞いたときに微調整が行われます。
つまり、限りなく正しい音を発音することで、口が音の出し方を学習します。そして、続いてネイティブの発音などで同じ音を聞くと、さらにその音を正しく調音するようにモーター理論が働くのでしょう。
さて、この段階ですでに聞き取れていることがお分かりでしょうか。真似をしている分には、聞こえてくる正しい音と、自分の発する音は一致しません。しかし、正しい音を発音できるようになれば、聞こえてくる正しい音と、自分の発する音が一致するようになると考えることができるのです。この辺りは、更なる研究が求められる分野です。
英語の「音」を学ぶのは簡単
 さて、それでは、英語の正しい音をどのように学べるのでしょうか。
さて、それでは、英語の正しい音をどのように学べるのでしょうか。
これに関しては、もう山ほど書籍が出版されています。専門家でない人が書いたものもありますが、多くは専門家が書いているので間違いはありません。ただし、専門家が書いているので、面白くもおかしくも何ともないものが多い点も否めません。
第二言語習得の世界では、外国語の音の習得に関して、母語にない音は学習しやすく、l と r のように日本語のラ行に2つの音が可能性として存在する音や、似ている音の学習が難しいとされています。
これらの音素は、正しい調音点や調音方法を学ぶことでマスターできます。そして、正しく発音できるようになれば、聞き取りもしやすくなります。しかし、日本語と異なる英語の音を学ぶだけでは足りません。
英語の特徴として、子音連続や子音で音節を終わることが許されている点が挙げられます。これが厄介な現象を生み出します。語末の子音と語頭の母音がくっ付いてしまう再音節化という現象をはじめとして、弱化、同化、フラップや側面開放、鼻腔破裂など様々な現象が見られます。
例えば ‘come and go’ は日本語訛りの英語だと「カム アンド ゴー」となりますが、実際には「カミンゴウ」と聞こえる音になります。come の m と and の a がつながるだけなら「カマンゴウ」のはずですが、and の a は弱化していて曖昧母音になります。すると「ア」でもなく「イ」でもない曖昧な母音となります。
‘that man’ の t は m に同化します。つまり、’tham man’ となり t が消えます。また、’got you’ などでは ‘t y’ が同化して「ガッチュウ」のような音になります。
さらに、米語では ‘a lot of’, ‘butter’ のように母音の挟まれた t は弾音化して日本語の「ラ」の音になります。’water’ は「ワラー」’butter’ は「バラー」’better’ は「ベラー」のように発音した方が、より米語の発音に近くなるわけです。
それだけではありません。’puddle, riddle, little’ のように dl, tl が側面開放という舌の使い方で発音されます。d l では舌の位置が同じですが、d の構えをすると口腔内が閉鎖されるので空気が口から外へ出られません。一方の l の構えは舌先は d と同じですが、舌の側面に空気の通り道を作るので空気が口腔内から外へ抜けられます。そして、d の構えから舌先はそのままで、舌の側面から勢いよく空気を逃すと側面開放の音になります。「パドー、リドー、リロー」のような音になります。
同様に ‘kitten, mitten, sudden’ のような組み合わせでは、以下のようなことが起こります。まず e の音が脱落します。すると tn, dn という組み合わせが生まれます。これらの音の組み合わせは側面開放と同様に、同じ舌の構えをしています。ただ、n は鼻腔へ空気が抜けます。そこで、t や d で一旦舌先を解放して空気を逃して、再び n に向けて舌先を同じ構えにするのではなく、舌先は歯茎にくっつけたまま、軟口蓋を下げて鼻腔へ空気を抜くのです。すると「キ·ンー、ミ·ンー、サ·ンー」のような音になります。
このように英語の音素だけでなく、音節単位での特徴をも知ることが正しい調音(発音)を可能にします。大変でしょう。こんな内容を扱った教材はあまり聞かないので、時期を見て作ってみるかもしれません。気長にお待ちください。
日本語の知識の干渉を排除するのが大変
 さて、ここまで述べてきたように、英語と日本語は音声が異なるばかりでなく、音韻体系も異なります。その結果、日本語では起こらない現象が英語では頻繁に起こるようになります。
さて、ここまで述べてきたように、英語と日本語は音声が異なるばかりでなく、音韻体系も異なります。その結果、日本語では起こらない現象が英語では頻繁に起こるようになります。
ただでさえ、英語は15世紀に始まった大母音推移以降、音声と綴りが一致しなくなりました。それに加えて、上で述べたような音の組み合わせごとに、様々な変異が存在するのです。とはいえ、それらの変異は無限に存在するわけではありません。上で述べたようなパターンをマスターすれば、米語に関しては問題なく発音できるようになるでしょう。つまり、米語のリスニングに一歩近づくことになるわけです。
しかし、です、誠に恐縮ですが、音声や音韻規則の違いに加えて、「日本語の知識」が正しい英語の発音を邪魔していることがあるのです。
この点に関して、少しだけ触れておくことにします。
日本語には、「特殊拍」と呼ばれる音素があります。これらには「撥音」「長音」並びに「促音」があります。母音連続も特殊拍に数えられることがありますが、ここでは省くことにします。
さて、その特殊拍。何が特殊かといえば、「決まった音を持たない」点と、もうひとつ「モーラ(拍)を持っている」点が挙げられます。
「長音」は決まった音がなく、先行する母音などの音価をコピーして1モーラ分伸ばす働きがあります。例えば、「きて」と「きいて(きーて)」ではまったく意味が異なりますが、長音がしていることは前の音節「き」の母音「い」を1モーラ分伸ばしているだけです。
「促音」にも決まった音がありません。後続する子音の音価をコピーして1モーラ分の無声区間を作ります。例えば、「きて」と「きって」では何が違うかといえば、使用している音は同じですが、後続する「て」の構えで一拍分無音区間を作っている点です。しかし、促音も長音と同様に、そこにあるかないかで意味が変わる音素ということになります。
「撥音」は後回しにして、長音と促音の知識が、英語の発音にどのように影響するか見ることにします。
まず、長音です。日本語の二重母音「えい」「おう」はそれぞれ「えい」「おう」ではなく、長音「ええ」「おお」として発音されます。日本語では、例の塾は「けいおう」ではなく「けえおお」と発音されることになります。もちろん「けいおう」と発音しても良いのですが、そんなことをすると聞く人に違和感を与えることになります。
さて、この「えい」と「ええ」、「おう」と「おお」の例のように、日本語では二重母音を長音化させるのが自然ですが、英語ではそうはいきません。make を「メイク」でなく「メーク」といえば、通じないこともありませんが、違和感を与えます。しかし、「コウト(coat)」を「コート(caught, court)」と言ってしまうと、意味が通じなくなります。
このように、二重母音を長音化することは、日本語の世界では、誰も意識することなく自然に行なっており、逆に長音化しない方が違和感を与えます。しかし、この無意識の規則を英語に当てはめてしまうと、英語の正しい発音にはならないわけです。
次に促音です。促音は一拍分無音区間を作って意味を変えるのですが、英語の音をあたかも促音のように聞き取ってしまうことがあります。例えば、 ‘map, stop, split…’ などは日本語の音韻規則を適用すると、それぞれ「マップ、ストップ、スプリット」となります。
これらの語は、英語では1音節語ですが、日本語だとそれぞれ1音節3モーラ、1音節4モーラ、1音節5モーラです。これらの語を促音を交えながら発音することは、長音の場合ほど深刻ではありません。しかし、cat を「キャット」と発音するように促音部分で一拍無声区間を作ることがあります。十分に英語としては通じますが、正しい発音ではないことは間違いありません。
最も厄介な撥音
 さて、長音、促音の順に見て参りましたが、特殊拍の中でも最も厄介で、英語の発音にもリスニングにも多大な影響を与えているのが「撥音」です。
さて、長音、促音の順に見て参りましたが、特殊拍の中でも最も厄介で、英語の発音にもリスニングにも多大な影響を与えているのが「撥音」です。
撥音とは「ん」のことです。
撥音は、調音点を後続する子音から分けてもらうことになります。「本場、本田、本国」の中の「本」の/N/ の部分はそれぞれ順に [m, n, ŋ] となります。また、後続する子音がない場合には、先行する母音から影響を受けます。例えば「金、紺」は[kiŋ, koɴ]となります。[ŋ]は軟口蓋で、[ɴ]は口蓋垂で発音される音です。
日本語で話している分には、まったく問題は起こりません。また、それら「ん」の音が異なる音であることにすら気づかないで一生終わっていく方がほとんどでしょう。皆さんは知ってしまいましたが···。
しかし、この「ん」がローマ字の ‘n’ であると学校で教えられるあたりから、微妙な空気が流れ始めます。
逆にいえば、ローマ字を習った子は、その後英語を習うにあたって、英語の ‘n’ は「ん」と発音する、と(無意識に)勘違いしてしまうのです。そして、英語の ‘n’ を日本語の撥音「ん」に置き換えて発音します。こうなると、色々ややこしい問題が起こり始めます。
説明し始めると、これだけで論文をいくつか書かないといけない分量なので、簡潔に言います。以下のようになります。
’in a room’ という句があります。これを中学生あたりに読ませると、「イン ア ルーム」となります。「イン」の「ン」が語末なので、上で言うところの「金」の「ん」のように [ŋ] で発音、つまり [iŋ]と発音されてしまうのです。きちんと [n]で発音されていれば後続の [ə] とくっついて [nə] となりるところが、そうはなりません。この段階で再音節化が阻害されます。
さらにモーラの問題があります。英語に慣れて、発音も流暢になってきた中学生などは ‘in a room’ を「インナルーム」と発音したりします。まぁ、ちゃんと[n]と[ə]は再音節化されてくっついています。しかし、まだ問題があるのです。
「インナルーム」の「ナ」は良いのですが「ン」が余計です。本来なら「ん」つまり [n] は、 [ə] とくっついて [nə] となった瞬間に消えてなくなり [i.nə.rum] となるのです。しかし、そうはならずに [in.nə.rum] なってしまう。[n] がひとつ余計なのです。
英語の経験が長くなる帰国子女などは、「インナルーム」ではなく「イナルーム」と発音するのですが、留学生ではまだ「ん」が1モーラ分残ってしまうことがあります。
これが、ネイティブには違和感を感じさせます。
もちろん、十分に通じるので、それで良いじゃないか。それで良いのです。しかし、英語の音から始まって、音節を理解し、さらには日本語の知識が英語の発音に干渉していることを、知っているかいないかだけで、ずいぶんと英語の発音、ひいては英語のリスニングにも影響します。
さて、今回は英語の閾値から始まり、閾値を超えるために最低限必要な知識として、英語の音声や音韻の知識の話をして参りました。
外国語としての英語を正しく発音できる人が、同時に英語のリスニング能力も高いことはわかっています。また、音声や音韻に関することは、ある言語を習得する上で最初に行われることでもあります。
英語習得のために、正しい発音でたくさん読むことによる英語のインプットを実行するにあたり、まずは音の知識が重要であることをご理解いただければ幸いです。
【編集後記】
今回の記事をご覧になった方におすすめの記事をご紹介いたします。ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。
★パルキッズで育つ子の英語力の本当のところ
★英語教育 すすむ2つの二極化
★「インプット」で育てる「国語力」が学力すべての土台となります
★勉強する子に育てる方法
★完・船津流「育児論」
【注目書籍】『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)
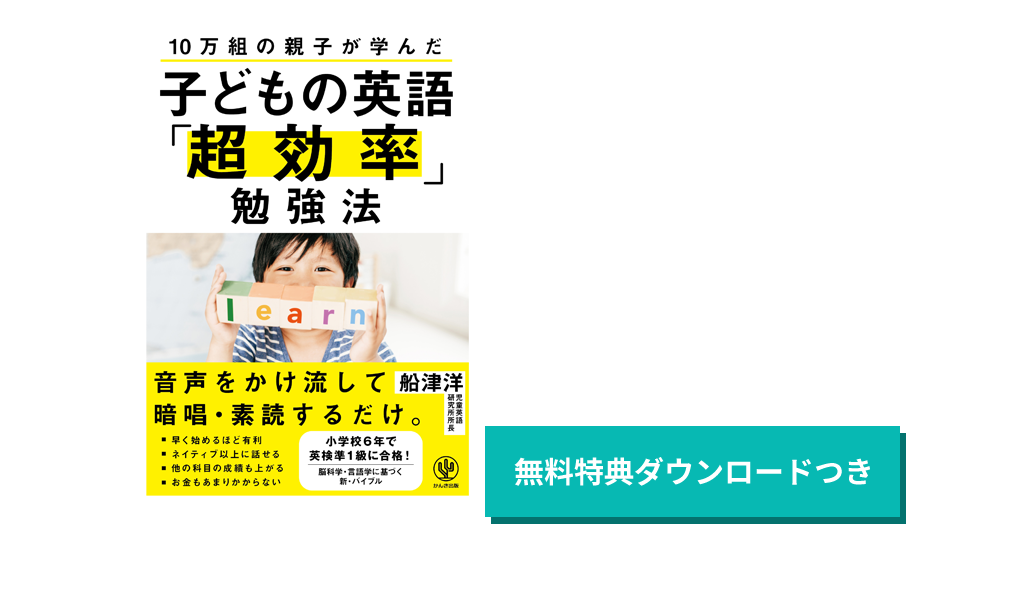 児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。
児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。

次の記事「取り組みに集中できる!子どものためのポモドーロテクニック」

船津 洋(Funatsu Hiroshi)
株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。