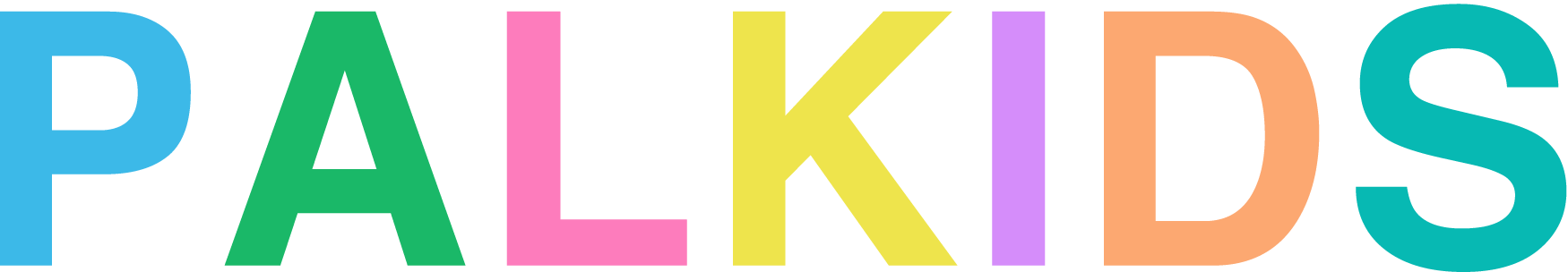パルキッズ通信 特集 | 大量インプット, 言語学, 言語獲得
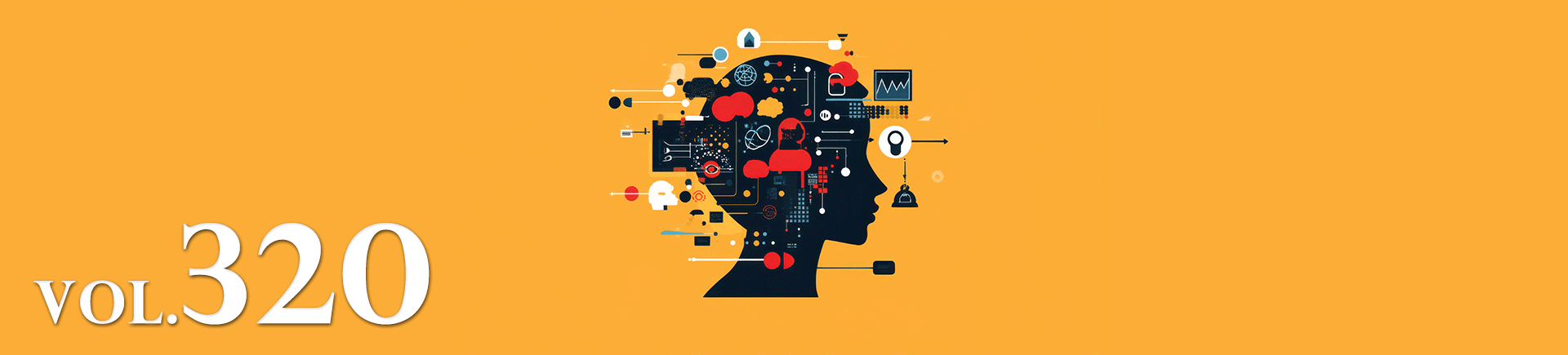
2024年11月号特集
Vol.320 | 言語獲得について現代の言語学でわかっていること
教育行政や業界に届かないアカデミアの情報
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
https://www.palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-2411/
船津洋『勉強のできる子はここが違う』(株式会社 児童英語研究所、2024年)
「成功」ではなく「失敗しない」ためには
 子どもの言語の獲得において、必要不可欠な習得要件があります。ひとつは連続音声から単語を切り出す能力で、もうひとつが他の言語の介入を経ることなく目的の言語を理解する能力です。生まれたばかりの赤ん坊が、彼らの育つ環境(例えば日本語)において、周囲の言語に晒されることで、音の中から単語を見つけ出し(言語学では「分節」と呼びます)、その単語に意味を付与していき、文全体の意味を頭の中でイメージ(認知科学では「心内表象」と呼ぶ)として描くことができる能力です。
子どもの言語の獲得において、必要不可欠な習得要件があります。ひとつは連続音声から単語を切り出す能力で、もうひとつが他の言語の介入を経ることなく目的の言語を理解する能力です。生まれたばかりの赤ん坊が、彼らの育つ環境(例えば日本語)において、周囲の言語に晒されることで、音の中から単語を見つけ出し(言語学では「分節」と呼びます)、その単語に意味を付与していき、文全体の意味を頭の中でイメージ(認知科学では「心内表象」と呼ぶ)として描くことができる能力です。
この能力を身につけるのに、おおよそ2年ほど掛かります。もちろん、その初期の段階での母語のレベルは、文法的にも語彙的にもお粗末極まりないのですが、言語獲得に必要な、分節と心内表象の回路を身につけていることは驚異的事実です。そして、「パルキッズ」ではこの直感的な言語回路を身につけさせることを、英語学習の基本中の基本と考えています。
なぜなら、英語における、この「直感的な言語回路」を身につけられる人が、日本人において極めて少なく、この回路を身につけずに、ダラダラと学習を進めている人が大半であるという現実があるからです。つまり、小学校から始めて大学まで、12年から16年かけて英語を勉強しても、英語を聞き取れないし、理解もできないという事実です。そんな状況を変えるために、「パルキッズ」をお役に立てていただきたいわけです。
しかし、なぜそのような不毛な状態が続いているのでしょう。
簡単な話です。先月号の『パルキッズ通信』や『英語子育て大百科』でも取り上げましたが、英語学習において「こうやれば良い」とか「私はこうやって成功した」という話ばかりが世の中に溢れていて、「なぜ、他の大多数の人々が英語習得に失敗するのか」に関しての情報があまりにも少ない、というのがその理由のひとつです。
成功するためにこうした方が良い、というN=1(サンプルが1しかない特殊な例)の背後には、様々な変数があります。また、成功者たちには共通点もあります。しかし、それらはあまり俎上に載せられることはないのです。
成功するコツを一言で言えば、「失敗しない」ことに尽きます。それでは、幼児たちは、どのようにして失敗せずに言葉を身につけるのでしょうか。あるいは、成功者たちは、どのように「失敗しない」で目的を達成することができたのでしょうか。
子どもたちの言語習得に関しては、古代ギリシャの頃から関心の的でした。言語は余りにも身近すぎて、言語を客観視するのには、相当な知力が必要となります。そこで、ものを考える性を持っている哲学者たちは、散々、言語とは?あるいは言語獲得とは?という点について考えてきました。そして、現在に至ることになります。その途次において、言語学の発展とともにわかってきたことがたくさんあります。
今回は、「言語学」の中でも、特に「音韻論」の知見から、子どもたちが、あるいは言語習得に成功した人たちが、どのようにして言語を身につけていくのかを見ていくことにしましょう。
Opacity(不透明性)の問題
 子どもたちが言葉を習得するにあたって、最大の不思議は不透明性と呼ばれる現象でしょう。言語は頭の中のイメージから、語彙を選んでそれを文法に照らし合わせて、最終的には音声として実現 (表出) されます。そして、子どもたちは、その音声を耳にすることで言語の体系を身につけていきます。
子どもたちが言葉を習得するにあたって、最大の不思議は不透明性と呼ばれる現象でしょう。言語は頭の中のイメージから、語彙を選んでそれを文法に照らし合わせて、最終的には音声として実現 (表出) されます。そして、子どもたちは、その音声を耳にすることで言語の体系を身につけていきます。
単語は色々と変化します。例えば、英語の過去形は動詞に /d/ をつけることで作ることができます。先行する子音が、無声子音の場合にはボイシングが同化して /t/ になりますし、歯茎破裂音(t d)が先行する場合には、発音の都合上 /ɪd/ になります。このような規則は、比較的簡単に学習できますね。
しかし、そうは問屋が卸さないケースもあります。例えば ‘man’ の複数形は ‘men’ ですし、同様に ‘foot’ の複数形は ‘feet’ です。’man’ はどう /z/ を付けてみても ‘men’ にはなりませんが、単語の元の形から複数形へ派生する段階で、単純に /z/ をつけるだけではなく、もう中間の段階が隠れているのです。
これはウムラウトという現象で、man > mann-iz > menn-iz > men と変化しているのです。後続する /i/ は舌が高い位置(歯茎に近い位置)で発音されます。対して /a/ は、低い位置(舌が歯茎から離れている位置)で発音されます。そして、先行する /a/ が /i/ に引っ張られて口が閉じ気味になり /e/ として実現されることになります。foot > feet, tooth > teeth, goose > geese, mouse > mice なども同様ですが、問題は、表出される周囲の音声環境から、子どもたちがなぜこれらの法則を自然と身につけられるのか、という点です。過去形の /d/ や複数形の /z/ のような単純な変化ではなく、変化の過程、特に中間にどのような変化系があるのかが見えないのに、どうしてこの規則を身につけられるのでしょう。
英語に限ったことではありません。日本語でも、なぜ /kaku/(書く)の過去形が /kaita/ になるのでしょう。これは「音便という現象だよ」と学校では習いますが、そんなことを教わる前から、子どもたちは /kak-u/ > /kak-ita/ > /ka-ita/ の変化を統計的に学習して /kik-u/(聞く)や /hak-u/(履く)なども、同様にイ音便で変化させます。それどころか /kag-u/(嗅ぐ)> /kag-ita/ > /ka-ita/ ではなく、ちゃんと濁音の特徴を /g/ > /t/ に移動して > /ka-ida/ とする規則まで適用するのです。
このような事実を持って「なぜ聞いた以上のことを知っているのか」という視点から、言語の生得主義(後で詳しく述べます)が生まれます。結論を先取りすれば、子どもたちは「環境内で聞いた音」を「統計処理」していて、「自分なりの規則」を身につけているのです。それによって、まだ習ってもいない動詞の活用や、音便などの音韻変化の規則を発話に適用していくのです。
本人すら知らない間に、子どもたちは「インプット」>「統計的処理」> 「文法の確立」 > 「正しいアウトプット」を行っているのです。すごくないですか?
ここでのキーワードは「インプット」と、その「統計的処理」です。以下、子どもたちがどのように、連続音声から分節・あるいは意味づけを行っているのかを見ていくことにします。
音の連続から語を見つける旅
 日々のインプットから、子どもたちはまず音素を見つけます。生まれたばかりの赤ん坊は、人間が発することができる音素、例えば口蓋垂(いわゆる “のどちんこ”)を震わせて発音するフランス語の /ʁ/ の音とか、アラビア語の吸着音なども、音素として聞き取る能力を持っています。日本人の幼児を対象とした実験で、生後9ヶ月くらいまでは英語の l r の区別がつくことがよく知られています。ところが、11ヶ月になると l r の区別をしなくなるのです。これは、普段聞き慣れている音にチューニングし、それ以外の音を「関係ない音」として注意を払わなくなること、あるいは無視することによると思われます。無駄なことはなるべくしない、最小限の努力で最大限の効果を得ようとする経済性の原理が働いているのでしょう。
日々のインプットから、子どもたちはまず音素を見つけます。生まれたばかりの赤ん坊は、人間が発することができる音素、例えば口蓋垂(いわゆる “のどちんこ”)を震わせて発音するフランス語の /ʁ/ の音とか、アラビア語の吸着音なども、音素として聞き取る能力を持っています。日本人の幼児を対象とした実験で、生後9ヶ月くらいまでは英語の l r の区別がつくことがよく知られています。ところが、11ヶ月になると l r の区別をしなくなるのです。これは、普段聞き慣れている音にチューニングし、それ以外の音を「関係ない音」として注意を払わなくなること、あるいは無視することによると思われます。無駄なことはなるべくしない、最小限の努力で最大限の効果を得ようとする経済性の原理が働いているのでしょう。
このようにして、子どもたちは生育環境にある言語の音素を、連続音声の中から切り出していくことになります。因みに音素とは意味を分ける音の最小単位の要素です。英語であれば、アルファベットがそれに(大まかに)該当します。例えば、dogでは d > h で犬が豚(hog)になりますし、g > tで犬が点(dot)になる、音素とはそのような単位です。
日本語の場合には、かな文字で表記されるので、英語とは少々事情が異なります。かなは音素の表記文字ではなく、音節の表記体系です。例えば、kita であれば、k > m で「来た」が「見た」に変わります。また t > sh になれば、「来た」が「汽車」になり意味が変わってしまいます。これが音素ですので、「かな」よりは小さい単位と理解してください。
日本語の音素は、母音と子音を合わせて30ほどです。それに対して英語は40くらいあります。子音では日本語に存在しない f, v, th, l などが特徴的です。それより大問題なのは、日本語には母音が5つしかないのに、英語はその倍以上ある点でしょう。英語の ‘cat, cot, cut, again…’ などの音は、英語では音素なので、ここが別の音素に変われば丸々意味が変わってしまうのすが、日本人の耳にはすべて同じ /a/ として処理されます。
自分が聞いている言葉にどのような音素が存在するのかは、日々のインプットにより、統計的に処理されます。そして、そこに存在しない音は、前述の通り無視されるようになるのです。
赤ん坊は、聞くだけでなく、同時に話す練習もしています。厳密に言えば、話す練習というよりはむしろ、聞いた音をどのように発音するか「確認している」ような状態でしょう。モーター理論という考え方では、幼児は聞いた音を口の中で再現しているのです。この様子は、実際に超音波を使用した実験などで確認されています。育児をしていれば、子どもたちが日々話す練習をしているのを目撃していますよね。喃語(英語ではbabbling)という現象です。両唇を使った b, p, m や、歯頸を使った d, t, n 、あるいは少し遅れて軟口蓋を使った g, k と、母音を交えて発声練習をしているのです。
これらすべて、インプットがないと何も始まらないことは自明ですね。さて、インプットからの音素の獲得を見てまいりましたが、次に音素がいくつかまとまって作り出す音節という単位を見ていくことにします。
音節の獲得
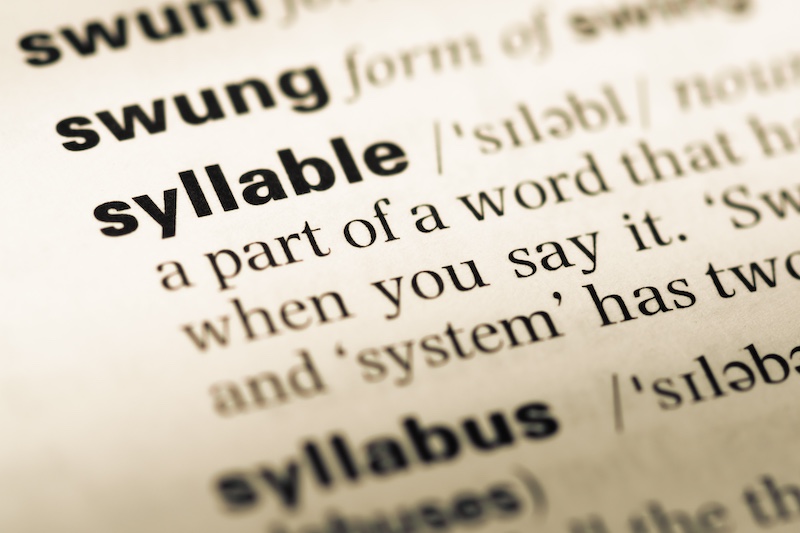 前節の、音素の部分では触れませんでしたが、音節の前に「有標性」という点に関して、ごく簡単に触れておくことにします。有標性とは、とある存在が基本的であり自然であるか、あるいは何か条件を追加したものであるかの指標を示す概念です。あるものが「無標である」というのは自然な存在であることを、「有標である」というのは特殊な条件が付与されていることを意味します。
前節の、音素の部分では触れませんでしたが、音節の前に「有標性」という点に関して、ごく簡単に触れておくことにします。有標性とは、とある存在が基本的であり自然であるか、あるいは何か条件を追加したものであるかの指標を示す概念です。あるものが「無標である」というのは自然な存在であることを、「有標である」というのは特殊な条件が付与されていることを意味します。
例えば、デフォルトの状態では口は閉じているので、口を閉じている状態が無標で、口を開けている状態が有標です。口を閉じている状態というのは両唇が閉じている状態で、その状態で声帯を振動させると /m/ になります。また、何か母音を発する場合、自然と「あー」となります。/i u/ よりも自然に母音を発声できるわけです。これが無標です。これらを合わせると「マンマン」となります。喃語の出来上がりですね。そこから、口蓋垂を閉じて「バババ」、声帯振動を制御すれば「パパパ」となります。
そして、言語発達ですが、無標なものから有標なものへと学習が進むと考えられています。音素の知覚や喃語の産出もそうですが、音節の習得も無標なものから始まるようです。
音節へ話を進めましょう。
上に「アルファベットは音素だが、かなは音節を表す文字体系」と書きました。音節とはよく聞こえる母音を中心として、その後ろにつくコーダ(coda : 音節末子音)と前につくオンセット(ons : 音節頭子音)で作られています。例えば、英語の ‘cat’(/kæt/)は核となる /æ/ に coda /t/ と ons /k/ がくっついてできている、1音節で成立している語です。対する日本語の /te/(手)や /me/(目)は、それぞれ核となる母音にオンセットが付いてできている1音節の語です。
英語にはコーダが付く語が多くて、日本語では撥音と促音(この議論には立ち入りません)を除きコーダは付きません。さて、世界の言語を見渡せば、音節にはコーダがないものが無標です。つまり、英語タイプよりも、日本語タイプの言語の方が多いのです。なんだか少し安心しますか?
音素がわかった後の音節の学習において、幼児たちはコーダのない音節を無標とします。例えば、 ‘make’ という1音節の単語。英語の発音は /meɪk/ ですが、日本人には /mee.ku/ (.は音節の境目)と聞こえます。英語ではコーダはOKなのですが、日本語では撥音と促音以外のコーダはNGです。そして聞こえている最後の /k/ に対して /u/ という母音をくっつけることで1音節を作り上げて、その結果、英語では1音節の /meɪk/ が、日本人にとっては2音節の /mee.ku/ になってしまうのです。
英語には、例えば ‘cat, dog, pan, book, desk street, ask…’ などなどコーダを含む1音節語が多くあります。同時に、特に前置詞や副詞の ‘in, on, at, up…’ や、冠詞 ‘a, an’ など母音で始まる使用頻度の高い語が多く、子音で終わる語にそれら母音で始まる語が後続することで、再音節化が起こります。つまり、コーダ子音で終わるのは有標なので、後続する母音が、オンセットとして先行するコーダ子音を吸い付けてしまうのです。/kʌm.ɑn.ɪn/ (‘come on in’) > /ka.ma.ni.n/ (「カマニン」)という具合に日本人に聞こえてしまうのは、そんな理由によるのです。
さて、音素から音節という単位を見て参りました。ここから語(形態素)という単位へ話を進めるのですが、その前にとても重要な「韻律(prosody)」に触れておかねばなりません。
ちょっと大変ですか?もう少しです。頑張ってください。これで、あなたも言語学者です。そんなものになりたくない?まぁ、そう言わずに。なぜインプットが大切なのか、なぜ「パルキッズ」で取り組むことが外国語習得の王道なのか、スッキリしますので、もう少しお付き合いください。
韻律の獲得
 さて、言葉を話すときには、ある程度をひとかたまりに話します。例えば、小学生のお子さんに、あるいは翌日のイベントに向けて「お蕎麦を食べる」と言ったとしましょう。これ、いくつに分けられますか?読みにくいかもしれませんが、説明の都合上、ローマ字に直させてください。すると、この句は ‘osobaotaberu’ と12の音素からなります。そして、(子音)母音のセットが音節ですので /o.so.ba.o.ta.be.ru/ と7つの音節に分けられました。さらに大きな単位で分けると /o/ /so.ba/ /o/ /tab/ /eru/ と、名詞や動詞とそれにくっつく接頭辞や助詞や活用の接辞の5つの単位にまとまりました。さらに大きな単位にすると、名詞句 /osobao/ と動詞句/taberu/ に分けられました。
さて、言葉を話すときには、ある程度をひとかたまりに話します。例えば、小学生のお子さんに、あるいは翌日のイベントに向けて「お蕎麦を食べる」と言ったとしましょう。これ、いくつに分けられますか?読みにくいかもしれませんが、説明の都合上、ローマ字に直させてください。すると、この句は ‘osobaotaberu’ と12の音素からなります。そして、(子音)母音のセットが音節ですので /o.so.ba.o.ta.be.ru/ と7つの音節に分けられました。さらに大きな単位で分けると /o/ /so.ba/ /o/ /tab/ /eru/ と、名詞や動詞とそれにくっつく接頭辞や助詞や活用の接辞の5つの単位にまとまりました。さらに大きな単位にすると、名詞句 /osobao/ と動詞句/taberu/ に分けられました。
もうひとつ重要な概念が、モーラ(拍 : 長さの単位)です。日本語は母音を核として、その前にオンセットが付いて所謂 “かな” の単位があります。このかなの単位をモーラと呼びます。モーラとは長さの単位で、通常の話し方だと1秒間に7モーラくらいが(速くも遅くもない)平均的な発話速度です。上の「お蕎麦を食べる」は7モーラですから、大体1秒かけて「お蕎麦を食べる」と言うことになります。ちなみに英語は1秒間に5音節くらいです。
ここからが本題。
漢語や外来語を除くと、日本語の語は2モーラが無標です。「やま、かわ、いけ、うみ、そら…」などなど2モーラが多いのが特徴です。同時に「ひとつの語は最も小さくても2モーラね」という制約が働いていて、京阪方言では「蚊、手、気」などを「かあ、てえ、きい」などと2モーラを保とうとします。
子どもたちは、2モーラをひとつの語の単位として分節する傾向があります。京阪方言の場合には、1モーラの語も2モーラで発話されるので問題ありませんが、東京方言では「2モーラ規則」が緩く、それらの語は「かに刺された」「はが痛い」のように1モーラで発話されます。すると子どもたちは、これらの文を裸助詞の「蚊」や「歯」を「カニ」や「ハガ」のように、2モーラでひとつの語であると分析します。結果として「カニに刺された」「ハガが痛い」のような発話となって現れるわけです。
これまた興味深いのですが、親も無意識のうちに、子どもには1モーラ語を2モーラに増やして話しかける傾向があります。「おくち」「おひざ」のような2モーラ語と同様に「おめめ」「おてて」と話しかけるわけです。これにより、子どもたちは上のような異分析(間違えた箇所で分節すること)を避けることができるのです。
これって、どう思いますか?子どもたちは「日本語は2モーラだよ」などということを教わって、あるいは考えながら分節しているわけではありません。周囲の話す言語のインプットから、自然と「日本語は2モーラ」という統計結果を導き出しているのです。統計を少しでも知っていれば、サンプルが多いほど精度が上がることはお分かりいただけるでしょう。子どもたちの分節においても同じです。インプットされるデータ量が多いほど、正確な分析ができるのです。
英語の韻律構造
 シェークスピアのソネットなどに触れたことのある方はご存知かもしれませんが、英語の詩などのリズムを表すのにトローキ(trochee : 強弱格)とアイアンブ(iamb : 弱強格)という韻律があります。英語はストレスアクセントで一定の間隔で「タンタンタンタン(下線部が強拍)」とリズムを刻みながら話されます。
シェークスピアのソネットなどに触れたことのある方はご存知かもしれませんが、英語の詩などのリズムを表すのにトローキ(trochee : 強弱格)とアイアンブ(iamb : 弱強格)という韻律があります。英語はストレスアクセントで一定の間隔で「タンタンタンタン(下線部が強拍)」とリズムを刻みながら話されます。
例えば、’I’d like to have some tea with you.’ という文は、’I’d like to have some tea with you.’ (下線部が強拍)というアクセントになります。ちなみに、例文からもわかるように、機能語(前置詞、代名詞、接続詞など文法的機能を果たす語)ではなく、内容語(意味内容を担う語)に強拍が置かれます。
さて、英語のリズムは、2モーラのトローキです。子どもたちは文(句)から単語を切り出すときに、「強拍から語が始まる」「2音節でひとかたまりだ」という自然の法則にも叶っている自らの分析結果を当てはめます。’like to, have some, tea with, you’ と切り出すことになります。例えば、’like to’ では内容語が先に理解されて、その後に時間をかけて機能語を語彙化していきます。
さて、英語では1音節語が多いのですが、もちろん2音節以上の語もたくさんあります。それらの語の分節も2音節のトローキリズムを基に行われます。例えば ‘banana’(バナナ)、2歳くらいまではこれを[‘nænə](ナナ)あるいは[‘bænə](バナ)と2音節のトローキで呼ぶ子が多い([‘]は強拍アクセントの位置)。これって、周囲の大人がそんなことを言うわけはありませんね。自分なりに、英語のリズムに合わせて切り出して発音しているのです。この一例を見るだけでも、子どもたちがインプットされた音声を自分なりに分析していることがわかります。
これは、英語に限ったことではありません。日本語では2モーラでしたが、イスパニア語でも、例えば、Fernando > mano、libro > pito と長い語は2音節、あるいは2モーラに切り取られて発音される時期があります。(なぜ nan > ma, lib > pi, ro > to と変化するのかについては、話の流れと関係ないので触れません)
このように長い語は切り取られますが、逆に短い語、つまり2音節/2モーラを満たしていない短い語は上の日本語の例で見たように2音節/2モーラに拡大することもあります。専門的には、「語の最小制約」という、ヒトの言語に普遍的な韻律化(一定のメロディーに乗せること)の規則に則っているようです。
上のお茶の例文(like to have some tea…)で見たように、文(句)の発話にもこのような韻律化の規則が適用されます。子どもたちはこの規則にとても従順で、語の存在よりも韻律を大切にしているような印象すらあります。例えば、’Tom hit the ball.’ は、下線部にアクセントを付けて発音されます。この中の機能語である ‘the’ は先行する強拍 ‘hit’ とペアになっている弱拍として実現します。しかし、 ‘Tom handed (the) ball.’ では、過去形の形態素 ‘ed’ が先行する強拍の ‘hand’ ペアの弱拍として実現させようとすると、’the’ をねじ込むことができなくなります。結果として ‘the’ が省略されてしまうことになります。もっとも、この現象も2歳半くらいまでには消滅して、’handed’ の ‘ed’ を短く発音することで、きちんと ‘the’ も入れ込んで発音するようになります。
いかがでしょう。このように、子どもたちはインプットからその言語特有の韻律特徴を捉えて、その韻律のパターンをもとに分節したり、あるいは発語したりしています。韻律特徴など、読むだけでも面倒ですし、大人でも理解するのに少なからずの知力を使います。そんなことを2歳の子どもに教えようにも、教えられるわけがありません。つまり、インプットから自然と身につけさせる以外には方法がないのです。
音素から始まり音節、さらには韻律構造の獲得までたどり着きました。もう少しです。残すは語(正確には形態素)の獲得と、語の意味の獲得です。このへんで伸びをしてひと休み、お茶でも飲んでから、引き続き読み進めてみてください。
語 (形態素) の獲得
 ここでは、語(形態素)について見ていくことにします。そもそも「語」とは何でしょう。色々な定義がありますが、一般的には独立して発話できる単位とされています。「いぬ、ねこ」などは語ということになります。しかし、独立して発話できないが、意味を持っていたり文法機能を果たす単位もあります。例えば「~が、~の」などの助詞や「と、や」などの接続詞、「たち、ら」などの接尾辞などがそれです。これらの独立して発話できないものと、独立して発話できるものも含めて形態素と呼びます。
ここでは、語(形態素)について見ていくことにします。そもそも「語」とは何でしょう。色々な定義がありますが、一般的には独立して発話できる単位とされています。「いぬ、ねこ」などは語ということになります。しかし、独立して発話できないが、意味を持っていたり文法機能を果たす単位もあります。例えば「~が、~の」などの助詞や「と、や」などの接続詞、「たち、ら」などの接尾辞などがそれです。これらの独立して発話できないものと、独立して発話できるものも含めて形態素と呼びます。
それを踏まえて。語の最小性制約では、2音節/2モーラが語の基本の形、つまり無標で、言語一般に共通している法則のようです。そして、3モーラ以上の語は切り取って2モーラにしたり、あるいは1モーラの語は2モーラに拡張して産出したりすると、見て参りました。
これは、自然の摂理に則っている無標性、あるいはそこに何らかの手を加えている有標性の違いとして理解されます。そして、一般的に無標(普遍的)なものから有標(個別的)なものへと学習が進んでいきます。
日本語はモーラタイミングの言語あることは、繰り返し述べていますが、実は、モーラは言語の中では有標で、逆に音節単位の方が無標です。つまり、日本人の子どもも最初は音節単位で分節しようとしますが、日本語の習得が進むにつれて、モーラ単位で分節するようになるのです。
例えば、「ブランコ」や「ベランダ」などは4モーラですね。日本語では、/bu.ra.N.ko/ /be.ra.N.da/ と、それぞれ4拍の語のはずです( /N/ は撥音、詳しくは『パルキッズ通信2024年4月号』参照のこと)。しかし、幼児はこれらを /bu.ran.ko/ /be.ran.da/ と3拍で分節します。つまり、日本人の幼児も、最初は音節単位で分節するのですが、それが成長とともに、特にかな文字を身につけると、モーラで分節するようになるのです。単純な因果関係で、かなで表されている音がモーラ単位である、というだけのことです。
さて、無標な要素から有標な要素へと学習が進む、と書きましたが、有標性以外にも学習に関与する要素がいくつかあります。頻度、親密度、近傍密度、そのほか音素配列規則などです。それぞれ簡単に説明すると、頻度とはインプットの頻度のことです。どれだけ繰り返し耳にするか、という指標です。親密度は、どれだけ身近であるのかという指標です。近傍密度は、似ている単語が多いかどうかの指標です。最後の音素配列規則は、言語特有の音素の並べ方の規則のことです。
この中で、形態素の習得に関しては、有標性よりも頻度のほうが大きく影響しているようです。つまり、インプットの頻度が高いものほど、聞き取ったり口にしたりする頻度が高くなるのです。また、親密度も影響しているようです。例えば、自分の名前や、一般語彙(身近なものの名前や動作の語)など親密度の高い身近な語も早く習得される傾向にあります。
頻度に関しては、音節構造の頻度、つまり英語のようなコーダ付きの音節を頻繁に聞くのか、あるいは日本語のようにコーダのない開音節を頻繁に聞くのかが、その習得の順序と相関関係にあります。より頻繁に聞いている方が、早く習得されるわけです。ちなみに英語では、コーダがある語が60%を占めるそうです。日本語では撥音(漢語などによく使われる「ん」)と促音( /kite/ [きて] と /kiQte/ [きって] では意味が変わりますが、それは促音 Q が無音の一拍を取っているから)を除けばコーダはありませんので、頻度は低いのですが、「ん」はよく使われるので、早い段階で学習されます。
また、音素配列規則も早い段階で習得されます。音素配列規則とは「この並びで音素を配列することを許可しますよ」という規則のことです。英語では、子音連続が許されていますが、何でもかんでも良いわけではありません。語頭では3子音の連続までで、’str, spr’ など必ず /s/ から始まらなくてはいけません。語頭の2子音は ‘sp-, st-, tr-, pl-‘ などは許可されていますが、’tl-, sr-‘ などは規則違反となります。
これらも特に誰に教えられるわけでもなく、インプットから単語のタイプ、音節の種類、耳にする頻度や、近傍密度など、子どもたちはせっせと統計を取っています。これらは恐るべきことなのですが、幼児たちは本人すら気づかないうちに、このような複雑な作業をコンピュータのようなスピードで行っているのです。
語の意味の獲得
 最後に、形態素の意味の獲得について、簡単に触れて終わることにします。
最後に、形態素の意味の獲得について、簡単に触れて終わることにします。
冒頭で言語の獲得とは「分節能力と心内表象化能力の獲得にほかならない」と書きました。ここまで分節能力の獲得について書いてまいりましたが、それでは半分しか達成されていないことになります。
もっとも、日本人の大半、というかほとんどが「英語が聞き取れなくて」困っている中、幼児たちが英語のインプットによって、英語の分節能力を身につけられるなら、それはそれは夢のようなことです。なぜなら、多くの日本人は中学・高校までにある程度以上の英語文法と語彙を学びます。それらを活かすことができない決定的な理由が「聞き取れない」ことにあるわけですから、この一点を突破できれば、英語は身についたも同然なのです。
しかし、それでも、英語を日本語に訳しているうちは、本当の意味で英語を獲得したことにはなりません。英語は英語のまま、日本語に訳すことなく理解できる、つまり耳から入った英語が、そのまま心内表象化される、そんな能力を身につけてこそ、ようやく「使える英語」となるのです。
日本語に訳さず英語を理解するなんて無理だ、などという声が聞こえてきそうですが、それは本当でしょうか。
例えば、’desk, dog, piano, department store…’ などの名詞を、日本語に訳す必要がありますか?そんなことはないはずです。では、’good, pretty, sick, dark, easy…’ などの形容詞を、日本語に訳す必要がありますか?そんなこともないはずです。では、’in (my room), on (the table), at (the office)…’ などの前置詞に訳が必要ですか?そんなことはないはずです。
それよりも、みなさんが英語の理解に困っているのは、単純化すれば、ピンポイントで動詞や副詞、あるいはその組み合わせの意味がわからないことによるのです。
コロナ騒動以降は中断していますが、児童英語研究所では、中学2年生向けの英文素読の講座を行っていました。この素読講座ではまず、開始前に自分の持っている英検の級の長文読解問題の部分だけ解かせます。とある受講生の解答を見て驚きました。英文の周りに、びっしりと日本語訳が書いてあるのです。わかりにくい部分だけならまだしも、日本語に訳すまでもなく理解できるような名詞や冠詞にまで、日本語訳が振られていました。そして、5~6時間の素読講座の後に、今度はひとつ上の級の長文問題を解かせます。すると、見事に日本語訳の書き込みが消えていました。これは、英文の素読によって、英語を英語のまま処理することに脳が慣れてきたためだと思われます。
ただし、名詞や形容詞などは良いとして、既述のように動詞や副詞、あるいはその組み合わせから生じるイディオムと呼ばれるものは、なかなか理解しにくいことに変わりはありません。
それでは、英語圏の子たちは、どのようにして語の意味を身につけていくのでしょうか。
この答えも単純です。同じ語を別の文脈中で聞くことで、語の意味範疇が定まってくるのです。例えば、英語の ‘drink’ は日本語では「飲(の)む」と訳されますが、このやり方ではうまくいきません。なぜなら、’drink’ と「飲(の)む」では意味のスコープ(範囲)が異なるからです。日本語では、薬も、飴玉も、条件も、あるいは息すらも「飲(の)む」ことができます。しかし、英語の ‘drink’ は「液体を咀嚼せずに体内に取り込む」ことのみを意味します。このあたりは拙著『たった「80単語」!読むだけで「英語脳」になる本』(三笠書房)に詳しいので、これ以上は触れません。また、面倒な副詞に関しても『たった「18単語」!読むだけで「話せる英語脳」になる本』(三笠書房)で紹介しているので、そちらを参照していただくことをおすすめします。
しかし、英語圏の幼児たちは、そんな本を読まなくても動詞や副詞の意味を理解するようになります。ヒトには、文脈から単語の意味の境界線を身につけていく能力があります。これは、皆さんにもあります。それが証拠に、最後に国語辞典をひいたのはいつですか?そうです。辞書に当たらなくても、新規獲得語の意味は、自然と身についていくのです。幼児であれば、なおさらのことです。
「パルキッズ」で育つ子どもたちは、このようにして自然と英語の意味を身につけていきます。ただし、彼らは通訳ではありません。つまり、英文の意味内容を心内表象できるようになったからと言って、それを日本語に訳して説明することができるかというと、これはまた別の問題となるわけです。
さて、今回は音韻の獲得から形態素の意味の獲得まで、長々と書いて参りました。音素も音節もモーラもあるいは韻律階層も、結果として大量のインプットから、子どもたち自身が統計を取りつつ獲得していく以外に方法はないのです。近年、音韻論・音声学の発見も、すべて同じ方向を、つまり「インプットが大切だよ」という方向を指しています。
「パルキッズ」でお取り組み中の皆様は、このまま安心して、日々淡々とインプットを続けていただき、お子様に英語の分節能力並びに心内表象能力を身につけさせてあげていただければ幸いです。
いや、本当に、よくぞここまで読んでくださいました。お疲れさまでした。
【編集後記】
今回の記事をご覧になった方におすすめの記事をご紹介いたします。ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。
★学校英語の理想と現実
★パルキッズで育つ子の英語力の本当のところ
★「インプット」で育てる「国語力」が学力すべての土台となります
★「主体性」の育て方
★「できない子」を「できる子」に変える方法
【注目書籍】『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)
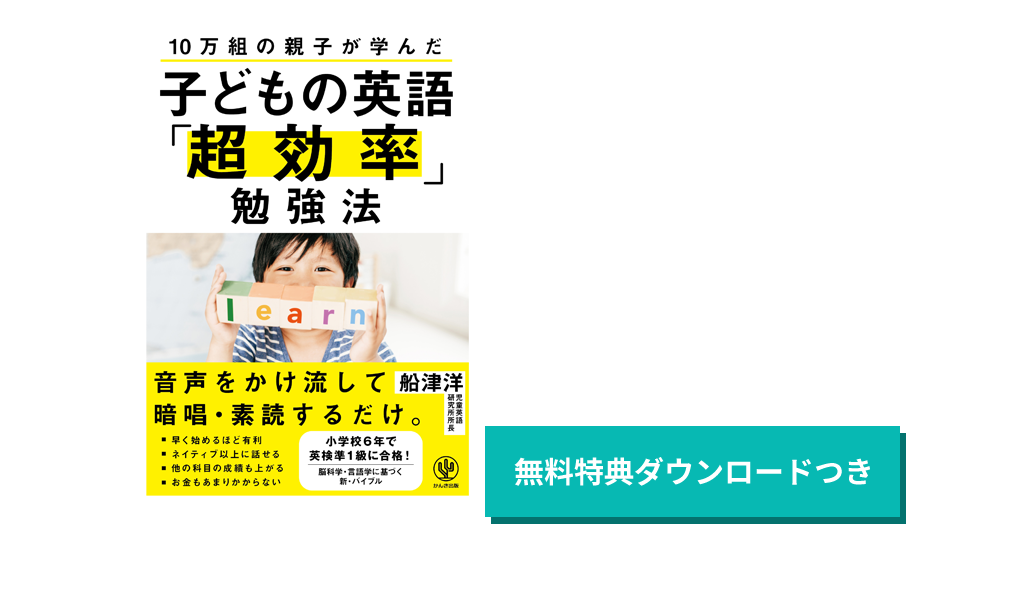 児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。
児童英語研究所・所長、船津洋が書き下ろした『子どもの英語「超効率」勉強法』(かんき出版)でご紹介しているパルキッズプログラムは、誕生してから30年、10万組の親子が実践し成果を出してきた「超効率」勉強法です。書籍でご紹介しているメソッドと教材で、私たちと一緒にお子様をバイリンガルに育てましょう。


船津 洋(Funatsu Hiroshi)
株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。