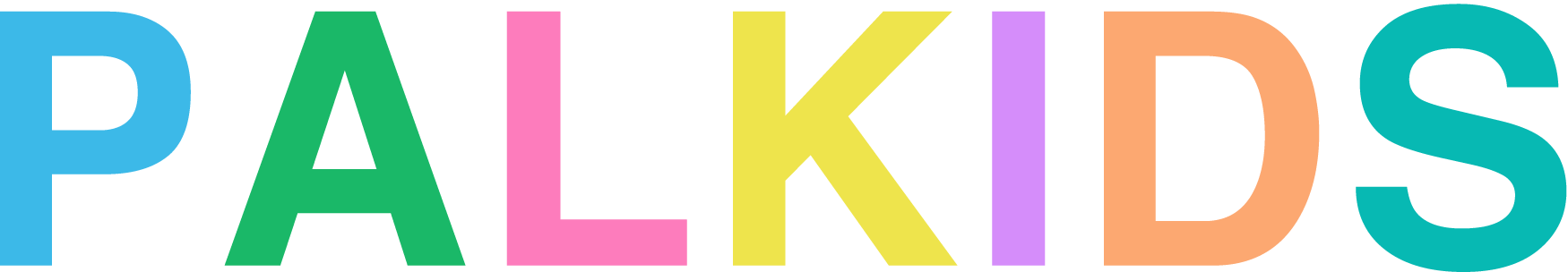パルキッズ通信 特集 | 子供の成長, 教育術, 日本の教育, 英語教育, 言語獲得

2016年9月号特集
Vol.222 | Perception before Production
英語学習の第一歩は「知覚」すること
written by 船津 洋(Hiroshi Funatsu)
※本記事のテキストは引用・転載可能です。引用・転載する場合は出典として下記の情報を併記してください。
引用・転載元:
http://palkids.co.jp/palkids-webmagazine/tokushu-1609/
船津洋『Perception before Production』(株式会社 児童英語研究所、2016年)
 いつまで経っても日本人の英語力は向上しない。そんな現状に業を煮やした世相を反映してか、大学の入学試験改革に伴う英語の選抜方式が大幅に変わるようです。従来の二技能~聞いたり読んだりする英語力~から、四技能~聞く読むに加えて、話したり書いたりする英語力~を測定するようになるそうです。今までの英語教育の諸種改革は棚上げし、まるで何事も無かったように、これからだ!と言わんばかりの中教審の論調には苦笑をこらえきれませんが、上記のような改革が進んでいくようです。結構なことです。
いつまで経っても日本人の英語力は向上しない。そんな現状に業を煮やした世相を反映してか、大学の入学試験改革に伴う英語の選抜方式が大幅に変わるようです。従来の二技能~聞いたり読んだりする英語力~から、四技能~聞く読むに加えて、話したり書いたりする英語力~を測定するようになるそうです。今までの英語教育の諸種改革は棚上げし、まるで何事も無かったように、これからだ!と言わんばかりの中教審の論調には苦笑をこらえきれませんが、上記のような改革が進んでいくようです。結構なことです。
ただ、この種の話、「四技能」とか「発信力」または「グローバル社会における…」などが持ち出されるとき、英語教育の現実から離れた「かけ声」だけがふわふわと浮遊する、上滑りの政策決定の印象を受けてしまうのは私だけなのでしょうか。そもそも何のための英語教育なのかといった英語教育のあり方や、使える英語力を求めるここ数十年にわたる世間の風潮、さらに近年では東京オリンピック熱に浮かれて近視眼的に叫ばれる「日本人のグローバル化」や「使える英語獲得論」の狭間で、「ああ、またか」と感じていらっしゃる現場の先生方も少なくないでしょう。
この手の論調は、別段中教審の提言に限ったことではありません。世の中で行われている英語教育や学習法にも通底しています。文法学習と単語の丸暗記ではダメだから「会話の練習をすべし」とか、日本人は引っ込み思案だから「とにかく外国人と積極的に話す場を持つべし」などなどです。これらの意見の背景には、学校の読解中心の英語では使い物にならないから、発話を中心としたコミュニケーション手段としての英語を身につけさせることが必要である、という考え方があるのでしょう。
しかし、このような「英語でコミュニケート」とか「英語で発信」のような考え方を目や耳にするにつけ、「何か大切なことをお忘れではないでしょうか」と疑問を投げかけたくなってしまうのです。
| Perception before Production
 ’perception’ とは「知覚」とでも理解しておけば良いでしょう。例えば、”That’s red.” と耳にして、この文章を “That’s led.”「(その物体は)鉛だ」ではなく「(その物体は)赤い」と理解することです。このように音素(この場合 ‘l, r’ )を聞き分け、意味の違いを理解することは perception(知覚)と言えるでしょう。つまり、とある文章、または単語を正しく知覚できたことを意味します。
’perception’ とは「知覚」とでも理解しておけば良いでしょう。例えば、”That’s red.” と耳にして、この文章を “That’s led.”「(その物体は)鉛だ」ではなく「(その物体は)赤い」と理解することです。このように音素(この場合 ‘l, r’ )を聞き分け、意味の違いを理解することは perception(知覚)と言えるでしょう。つまり、とある文章、または単語を正しく知覚できたことを意味します。
ある研究によれば、日本人は生後11ヶ月までは ‘l’ と ‘r’ の違いを知覚(perception)するのですが、それ以降の年齢になると、これら英語の音素の差異に関心を払わなくなります。他にも、’v, b’ や ‘th, f’ の違いなど、日本語の音素(※)には存在しない(日本語では音素の違いとして知覚されない)音に関しては無関心になるのです。そして、’v, b’ も同じ「バ行」の音、’th’ は「サ行・ザ行」、’f’ は本来の擦過音(こする音)としてではなく「ファ、フィ、フ、フェ、フォ」の最初の子音として認識するようになります。(※:「音素」とは、日本語で言えば「ジャリ・シャリ」の「ジ・シ」ように、また英語なら ‘red, led’ の ‘r, l’ のように単語の意味を変える音の最小単位を指します。)
1歳にもなると、周囲で話される言語(日本語)の音素を既に理解しているので、それ以外の音(日本語に存在しない音素)を耳にしても、区別しなかったり、日本語にある似た音素として認識したりするようになります。これは言語獲得や使用においては極めて自然なことです。日々使用する言語に関してはエコノミーの原理が働いて、最小限の労力で(つまり関係のない音には関心を払わないで)最大限の効果(つまり知覚や産出。「産出」に関しては後述)を行おうとするのです。
ただ「生後11ヶ月で ‘l, r’ の聞き取りができなくなる」のではなく、これはあくまでもエコノミーの原理に基づいて、日本語での生活に不要な英語特有の音に関心を払わなくなるだけです。幼児でも中学生でも、それこそ大人でも、正しい発音を理解すればこれら英語特有の音素も聞き取れるようになります。
| 産出の前に知覚
 ”Perception before production” とは、日本語に訳せば「産出の前にまず知覚」とでもなるのでしょう。言語学の世界では、所々でこの表現にお目にかかります。
”Perception before production” とは、日本語に訳せば「産出の前にまず知覚」とでもなるのでしょう。言語学の世界では、所々でこの表現にお目にかかります。
先ほどの例で言えば、幼児は正しい発語(産出)ができるようになるずっと前から、正しく語を知覚します。‘led’ と ‘red’ の違いを正しく発音できなくても、だからといってそれらの音の違いが知覚できていないと考えるのは誤りなのです。
英語の母語話者の幼児たちも、その発達段階でさまざまな不完全な発話(産出)を行います。例えば、’out’ の ‘t’ を落として[æu]と発音してみたり、複数の連続する子音をひとつの子音に省略して ‘step’ を [dep]、’floor’ を [fər] と発音することがあります。またアクセントの来ない音節を省略して、’banana’ を [næna] と言ってみたり、’noodle’ を [nunu] と言ったりもします。さらには ‘rock’ を [wak] と発音するなど、様々な音韻的な暫定的代用が発話時に行われます。しかし、これは彼等がそれらの音を正しく聞き取って(知覚して)いないのではありません。単に発音が巧くできていないので、発音しやすい音に置き換えているだけなのです。
音素の聞き取りと発声に関しては、このように “Perception before production” という考え方が正鵠を得ていることはわかりましたが、この考え方の当てはまる現象はこれに留まりません。
| 羊も馬も「ワンワン」
 子どもたちは様々な推測を行いながら、言葉を身につけていきます。言葉を身につける過程においては、大きく分けてふたつのことが行われていると考えられます。ひとつは当然のことながら「語彙の獲得」で、もうひとつは「文の構造の理解」です。(文の構造に関しては紙数の関係で今回は触れません)語彙の獲得の中では、様々な言い換えが行われます。先ほどの音の問題と同じように、幼児があれやこれや推測しながら語彙を増やしていく過程でも、「わかってはいるけど正しく言えない」ことがたくさんあるのです。
子どもたちは様々な推測を行いながら、言葉を身につけていきます。言葉を身につける過程においては、大きく分けてふたつのことが行われていると考えられます。ひとつは当然のことながら「語彙の獲得」で、もうひとつは「文の構造の理解」です。(文の構造に関しては紙数の関係で今回は触れません)語彙の獲得の中では、様々な言い換えが行われます。先ほどの音の問題と同じように、幼児があれやこれや推測しながら語彙を増やしていく過程でも、「わかってはいるけど正しく言えない」ことがたくさんあるのです。
幼児は1歳半くらいから急速に語彙を膨らませていきます。その過程では、次のようなルールが適用されています。
まず、「名前」は対象物全体を指すという前提で知覚します。白いウサギをみせて「うさぎ」という名前を聞くと、「うさぎ」とは「耳の長い白く丸い生物」と覚えます。ウサギの「耳」や「白さ」や「丸っこい生き物」といったひとつひとつの特徴ではなく、全体で「うさぎ」と理解するわけです。
また、たとえば「うさぎ」が特定の対象物ではなく、その種全体を指し示すと前提します。つまりたくさんいるウサギの中で、特定の1匹を「うさぎ」と呼ぶのではなく、同じ種類の生物もすべて「うさぎ」であると理解します。言ってしまえば、まずは名詞を「一般名詞」と前提すると考えれば良いでしょう。
さらに、見た目や行動の似たものも「うさぎ」であると認識します。したがって、茶色いウサギや耳が短いウサギも、ぴょんぴょん跳ねたりするような類似の行動を見せれば「うさぎ」であると類推するのです。
「一般名詞」「固有名詞」の区別に関して言えば、英語では冠詞(’the, a’)の有無や複数形になるかどうかといった点も、子どもたちは参考にしているようです。この点においては冠詞や複数形のない日本語を母語にする子は、英語圏に育つ子よりも手がかりが少ないのかもしれません。
ざっと上記のように、子どもたちは物の名前を覚えていくのですが、その過程で様々な言い違えをします。丸い果物は、ミカンであってもメロンであっても「りんご」と呼んでみたり、農場で見かけるウシやウマ、ヤギやヒツジをすべて「ワンワン」とか、英語であれば ‘doggie’ と呼んだりします。
さて、ここで考えてみてください。お子さんたちがこのような言い違えをしたときに、皆さんはどんな反応を示しますか?ある親御さんはそれらを我が子の「迷言集」として記録するかもしれません。また、親御さんが言語学者なら、詳細な観察記録を取るでしょう。しかし、どうでしょう。「こんな単語を覚えていないとは何事だ!」と怒り出したり心配したりする親御さんは皆無でしょうし、いちいち訂正する方も少ないでしょう。大抵は「そうね、お馬さんがいるわね」などと発語自体を肯定してから、それとなく正しい言葉を添える程度ではないでしょうか。
しかし、これが母語である日本語ではなく、身につけさせたい英語となると反応は一変します。「違うでしょう。これは ‘horse’ でしょう!」と否定から入って、ひょっとすると徹底的に訂正するかもしれません。なぜ日本語だと大目に見て英語だと途端に態度を一変させるのか、という精神分析は専門家に譲るとして、少なくとも常識的に考えて子どもの発話(特に学習中の外国語)に対して、否定的な言葉をかけるのは避けた方が賢明です。
| 意図的に代用している?
 少し横道にそれましたが、子どもたちの発話には、発音を含め、正しく運用するに至るまでには、言い違えなどの様々な過渡的段階があることがおわかりいただけたと思います。しかし、ここで留意しなくてはならない点は、彼等は「”常に”間違えながら覚えていくのではない」という点です。実は間違えているどころか、かなり意図的にそれらの言い違えをしているのです。
少し横道にそれましたが、子どもたちの発話には、発音を含め、正しく運用するに至るまでには、言い違えなどの様々な過渡的段階があることがおわかりいただけたと思います。しかし、ここで留意しなくてはならない点は、彼等は「”常に”間違えながら覚えていくのではない」という点です。実は間違えているどころか、かなり意図的にそれらの言い違えをしているのです。
その根拠として第一に上げられる点は、該当する語を獲得した時点で言い違えが消滅することでしょう。たとえば、ネコを「わんわん」と呼ぶ子、英語であれば ‘doggie’ と呼んでいる子も「ねこ」または ‘cat’ という語を獲得すれば代用は行わなくなるのです。この点から考えれば、子どもたちは「わんわん」なり ‘doggie’ なりの言葉を、広く一般的に四足歩行の動物を指すために、一時的に代用していて、語が増えるにつれてその代用の割合も減少していくと考えられるでしょう。
子どもたちが特定の語を知っていにるも関わらず、その語を別の語で代用していることを示すふたつ目の根拠は、この言い換えの現象が ‘perception’(知覚) ではなく ‘production’(産出)においてみられる点です。これはとても重要なポイントです。
ウマやヒツジを「わんわん」と呼ぶ子に、たとえば、ウマとイヌの絵を見せて「お馬さんはどっち?」と尋ねれば、イヌではなくウマの方を選びます。同様にヒツジとイヌの絵を見せて「羊は?」と問えば正しい絵を選べます。つまり、「知覚」はできているのです。しかし、産出をしていない、もしくは産出はできていません。このように、幼児の言語発達においては “Perception before production” の現象が随所に見られるのです。
| ものには順序がある
 考えてみれば当然のことです。まず理解できるようになってから、すべての作業が始まります。まるで理解できていないのに聞き覚えだけあって、意味不明の単語の羅列を発話しながら、幼児が言語を身につけるとは考えられません。赤ちゃんたちは、まず相手の言うことを少しずつ理解できるようになり、理解できている語集団、つまり語彙を膨らませていきます。しかし、知っている語をすべて口にするわけではありません。わかってはいるけれど口にしない語がたくさんあるのです。繰り返しになりますが、まずは「知覚」です。そしてその後にゆっくりと「産出」が始まるのです。
考えてみれば当然のことです。まず理解できるようになってから、すべての作業が始まります。まるで理解できていないのに聞き覚えだけあって、意味不明の単語の羅列を発話しながら、幼児が言語を身につけるとは考えられません。赤ちゃんたちは、まず相手の言うことを少しずつ理解できるようになり、理解できている語集団、つまり語彙を膨らませていきます。しかし、知っている語をすべて口にするわけではありません。わかってはいるけれど口にしない語がたくさんあるのです。繰り返しになりますが、まずは「知覚」です。そしてその後にゆっくりと「産出」が始まるのです。
これは、言語習得全般に通じます。大人の外国語学習においても同じことが言えます。たとえば、未知の言語・ラテン語の単語を100個覚えたとしましょう。それでもって、ラテン語話者(もはやネイティブスピーカーは存在しませんが…)と会話をしたところで、お互いの意思を通じ合わせるようになるものでしょうか?まず重要なのは、会話ごっこではなく、「相手の言っていることを正確に理解できるだけの理解力」です。相手の発話を語単位に切り出して正確に知覚し、さらに句や文章の意味を正確に理解する。これが言語理解の第一歩ではないでしょうか。
外国人相手に、むやみやたらと限られた語を弄んだとして、一体その先に何があるのか、少し冷静になって論理的に考えてみれば自明でしょう。つまり、理解(知覚)が先にあり、その後に発話(産出)というのが、ものの順序なのです。
ところで、現在の学校英語で問題になっていることは何なのでしょう。「使える英語」を身につけられない、と非難されますが、使える英語の第一歩は何でしょう?まずは読んだり聞いたりして理解できることではないのでしょうか?そして、その後に話したり書いたりしつつ自らを表現する(日本人は日本語においてすら自ら表現することが苦手なので、まずは日本語での「自己表現」の授業でも行えばなお良いでしょう)、これが物事の順番です。
それでは、私たち日本人は、第一歩目であるところの英語の「知覚」はできるのでしょうか?洋画を字幕なしで見て理解できるのでしょうか?英書で小説を読んで理解できるのでしょうか?
この点に関しては少し説明がいるので付け加えると、英書で小説を読めるというのは、「日本語に訳すことができる」という意味ではなく「英語を英語のまま理解できる」ことを意味します。同様に映画を見て理解できるというのは、台詞をいちいち日本語に訳しながら理解するのではなく、英語のまま直感的に理解することを意味しています。特に生の英語、本来的な英語の理解は、音声英語を理解できることに他なりません。生の英語の実践の場では、相手の発言を日本語に訳したり、台詞を日本語に訳している暇などないのです。
まずは、以上のように、読んだり聞いたりした英語を直感的に知覚できる力を身につけなければ、「使える英語」への第一歩とはならないのですが、一体全体どれほどの割合で日本の高校3年生たちが、このような英語の知覚能力を身につけているのでしょうか?難関大はもちろんのこと、超難関大学に入るほどの知的格闘力のある大学生たちですら、学部によっては「英語はわからない・苦手」と言っているのです。いわんや残りの9割以上の高校3年生たちの英語力は、推して知るべしでしょう。
このような状況が、日本の英語教育の現状なのです。「知覚」すらできない子たちが大半なのにも関わらず、これからは「産出」を求めるというのですから、現場の先生方、そして改革後の大学選抜試験制度と格闘しなくてはいけない若者たちには、「お気の毒様」としか言いようがありません。
さて、今回は “Perception before production” という考え方を中心に書いて参りましたが、これは現在お子様に英語教育を実践中の読者の皆様には、是非とも肝に銘じていただきたい概念でもあります。最近でこそ少なくなりましたが、以前は「うちの子は英語で話してくれないんです」というお悩みが数多く寄せられていました。しかし、そんな親御さんたちとのやりとりの末に、毎回必ずと言って良いほど明らかになるのが「子どもたちは英語を知覚できているが、単に産出していない状況にある」という点なのです。今後は日本語なり英語なりの発達を見るときに、我が子が「どれだけ産出するか」ではなく、「どれだけ知覚できているか」に視点を移してみましょう。思いの外、理解が進んでいる我が子を発見できるはずです。

船津 洋(Funatsu Hiroshi)
株式会社児童英語研究所 代表、言語学者。上智大学言語科学研究科言語学専攻修士。幼児英語教材「パルキッズ」をはじめ多数の教材制作・開発を行う。これまでの教務指導件数は6万件を越える。卒業生は難関校に多数合格、中学生で英検1級に合格するなど高い成果を上げている。大人向け英語学習本としてベストセラーとなった『たった80単語!読むだけで英語脳になる本』(三笠書房)など著書多数。